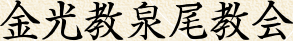大恩師親先生教話選集『聖地を頂く時』より
泉尾教会では、2027年にお迎えする御布教百年記念大祭を目指して、全信徒を挙げて信心の立て直しを図っておりますが、あらためて大恩師親先生のご信心を頂き直すための縁(よすが)として、本誌の誌面を借りて、大恩師親先生のご教話を年代順に紹介してゆくことにしました。
最初は、無残な無条件降伏によってゼロからの再出発になった日本の復興という厳しい時代背景に加えて、相次ぐ自然災害や経済的困難の中を雄々しく立ち上がり、6000坪の聖地泉光園を頂かれるまでの大恩師親先生のご信心の軌跡を昭和22年(1947年)から紹介してゆきたいと思います。
『神の願いに添う祈りを』
「祈りのない宗教は、死せる宗教である」と申し上げてもよいと思います。
祈らずにはいられぬわれ―限りある自分の力が判り、人生の
しかし、その祈りは、ただ自分の願望成就の祈りではなく、ただ神様の前にいろいろの願いごとを申し上げるのみでもなくて、生活全体の祈り、お互いの生活そのものが祈りでなくてはならないのです。
例えば、商売にいたしましても、神様に商売繁盛を祈るのみでなくて、商売全体が祈りでなくてはなりません。自分が幸福になるように祈るよりも、まず、幸福であるように自分の生活全体を整えるということが、私の分かってほしい祈りなのです。
一般的に日本の人々の祈りは、ただ「こうありたい」という、その都度その都度の祈りです。そんな祈りでは、本当の救いを頂くことはできないと思います。それも、祈りの一部ではありますが、私の申します祈りは、そんな一面的な祈りではなく、生活全体の祈りであっていただきたいのです。
「祈りはいのち」であります。信仰のいのちであり、全生命の泉であり、人生の根であると思います。
また、「なんでも!」の精神の現れが祈りであり、いかなる問題にも屈せぬ元気が、祈りの姿であると思います。「一心の祈り」とは、迷わず、神様・霊様へ突進する姿であると思います。おかげを頂くまでは迷わず、
その祈りは、ただ表面のおかげのみを追う祈りであってはならないのです。いわゆる「おかげ信心」や「祈り信心」に終わってはならないのです。皆さんには、そこをよくよく解っていただかねばなりません。
祈りの本質は、利己的願望成就だけでなく、神様のお祈りを頂くことであると思います。「神様の私に対するお祈りはどんなお心なのか? また、神様の私に対する思召しはどうなのか?」ということを解らせていただくための祈りでなければならないのです。
ですから、私の申し上げる「祈り」とは、単なるお祈りというよりも、神様のお心、神様の思召し、お祈りをお伺いすることなのです。お祈りというよりもお伺いです。神様がお互い(われわれ)に「かくあれ。こうせよ」と命じてくださっている。また「こうなってくれ」と頼まれていることを解らせていただくことが、祈りの
「なにとぞ! なにとぞ!」と一生懸命にお願いするのも、祈りの一面ではありますが、また、神様と差し向かって静かに祈らせていただき、神様の思召し、神様の自分に対するお声を聞かせていただかねばならないのです。
その祈りを一心に進めさせていただきたいのです。「こうしてくださいませ」との願望は、祈りの一部に過ぎぬと思います。どうも皆さんは、「神様がどんなに私を思召されているか。どれほどお恵みを垂れて下さっているか」ということが、本当に解らぬのではありますまいか?
それが解ってこなければ、信心の本道に入ることができないのです。本当の祈り、揺るがぬ祈りにならないのです。例えば、子が親に孝行するにしても、親の思いが解らない一方的な孝行だけでは、本当の孝行と言えないのではありますまいか? まず、ご両親様の思い、思惑を解らせていただき、その線に添わせていただくことが孝行の本道と思います。
神様は、この至らぬ私たちをどう思召しくだされているのか? 飛び込んで来るのを、どんなにお待ち受けになっておられるか…。「こんなにまで祈っている、思っている神の思いを、なぜお前たちは解ってくれぬのか?」という神様の悲願を解らせていただけるはずです。その次に「こうなってくれ。こうあれ。こうせよ」と仰せられるお心が解らせていただけるはずです。
「こうしてもらいたい。是非これを
しかし、世の中の多くの人々は、神様への讃美、神様への感謝がなくて、ただ「
どんなに淋しい、味気ない人生であっても、自分に対する神様の大きな温かい祈り、思召しが解ってくれば、人生の苦しさも
私は、前々から「なぜ、人は自分本位のお願いしか解らないのか? もっと大きな願いをしないのか?」と不思議に思っておりました。たとえ、祈って腹痛がおかげを頂き、喜んでも、次は頭痛…。これをおかげ頂いても、また腰痛…。また祈る…。おかげを頂く…。愚痴と喜びの繰り返し。即物的なおかげを追う信心。自分の祈りのみを通そうとする一方的な祈りでは、本当の安心、落ち着きは得られぬと思います。
神様の祈りに添うて祈る…。その祈りこそ、本当の救いを頂く祈りであり、この祈りこそ、永遠に続く祈り―「われ、神を宿せり。われ、神と共に生きる」の祈り―であり、この生活全体の祈り―信心生活―この祈りの生活を皆さんにもしていただきたいのです。お互いは、たとえどんな苦難に遭っても、私の言う祈りを切らしてはなりません。
神様への道を歩み、また神様の愛に包まれている自分である。どこにどう住もうとも、常に祈り抜き、神様に祈りを通わさねばならないのです。祈り貫き、足らざる自分に足していただく祈りを続け、その生活を通すのです。「やらせてくださいませ!」の祈りが、すべての根であり、泉であると思います。
生活の中に、「なんでも!」の意気込みが流れている祈りをしていただきたいのです。力強い生活…。「ああ、苦しい」と言うのではなく、苦に抑えられぬ強い祈りです。
ことに当たって、「嫌だなあ」と
しかし、たいていの人は、その祈りを頂かずに「適わぬ時の神頼み。ああ、仕方がない。神様にでもお願いしようか」と言います。「でも」付きの祈りに止まっております。「でも付き祈り」でなく、「なんでも!」の力強い祈りであってください。
神様が私たちを祈ってくださっていることを解らせていただく祈りを続けることです。その神様の祈りと私たちの祈りが、ひとつに溶け込むところに動かぬ感激があり、揺るがぬ救いがあるのです。そこに「神も立ちゆき、氏子も助かる」(『立教神伝』)道があると思います。
祈り抜いてください。本当のおかげを頂くまで…。「
(1947年4月 ある日の教話)