レルネット主幹 三宅善信
▼いろんな宗教が通り過ぎた島
6月の末にインドネシアを訪れたことは、既に7月14日に上梓した『豊葦原瑞穂国は何処に…』で報告した通りであるが、その作品では、日本からのフライト便の関係で、本来の目的地であったジョグジャカルタ(Yogyakarta)へ行くまでに立ち寄ったバリ島での話を主に採り上げたので、今回はその続編として、インドネシアの「メインランド(本土)」ともいえるジャワ島での見聞について述べたい。
私は、6月24日から28日までの日程で、インドネシアの古都ジョグジャカルタ(註:NHKの『アジア古都物語』でも紹介されていた)で開催されたACRP(アジア宗教者平和会議)第6回大会に出席していたのであるが、会議(註:北朝鮮の代表も正式に参加している)の内容も興味深い(註:アジア各国の代表からアメリカの対アジア政策に反対の大合唱が起った)ものがあって、私が現地で取材を受けたことがジャパンタイムズにも特集記事として紹介されていたりしたが、個人的により興味があったのは、火山列島であるインドネシアという国の風土、なかんずく宗教と山の関係についてであったことは言うまでもない。

メガワティ大統領も私の直ぐ傍の席に座られた |
まず話の前提として、インドネシアという地域の歴史的・宗教的背景を概述しておく。太古の昔、ユーラシア大陸の南東部からオセアニアにかけて、スンダ大陸という陸橋で連なっていたこの地域が、その後の海面上昇によって13,000の島々からなるスンダ列島を形成するに至ったこの島嶼国家は、人類学的にも、その拡散について非常に興味深い地域(註:ピテカントロプスと呼ばれるジャワ原人が暮していた。他にも、アフリカ大陸以外で唯一の大型類人猿オランウータンが生棲していることも興味深い)でもある。有史時代に入ってからだけでも、もともとあった土着のアニミズム的信仰に加えて、宗教的・文化的には常にインド文明から大きな影響を受けてきた。現在の国名である「インドネシア」も、「インド」プラス島々を意味する「ネシア」が引っ付いてできているくらいである。

ホスピタリティの国インドネシアでハーレム気分に浸る |
最初に、インドから伝わった創唱宗教は仏教であった。次に、インドで仏教が密教化し、民間信仰であるヒンズー教に呑み込まれていって消滅したのと同じ理由で、コテコテの民間信仰であるヒンズー教がこのインドネシアの地にも拡散してきた。最後に、インドがイスラム諸帝国の支配を受けるようになった時代(註:西欧が大航海時代を迎えるまでは、インド洋の制海権は、アラビア商人たちが握っていた。その前のローマ帝国時代は、インド商人たちが貿易風を活してインド洋の制海権を持っていた)には、インドネシアにもイスラム教が大々的に入ってきた。現在、インドネシア人の大多数がイスラム教徒であるのは、そういう訳である。この国では、街中のいたるところに、モスクが建っており、ラウドスピーカーから、大声量でコーランの聖句を流している。仏教やヒンズー教は、ほどんど遺跡でしかその形跡を留めていないが、辛うじて、「本土」ジャワ島から切り離されたバリ島に、ヒンズー教が土着している程度である。しかし、日本と同様、高温多湿で米食が基本のこの国では、イスラム教といっても、砂漠地帯のアラブやアフガンのような原理主義的なそれではなく、他の宗教文化にも寛容である。
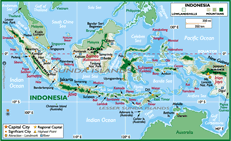
スンダ列島の島伝いに生物も文化も伝播していった |
さらに、近世に入ってからは、オランダの東インド会社経営(胡椒やコーヒー栽培のためのプランテーションにされた)に見られるように、西欧植民地化の影響を受け、一部では、キリスト教化した島もある。なぜ、東ティモール問題が、これほど国際的な注目を浴びたかというと、その最大の理由は、東ティモールに住む人々の過半数がキリスト教徒(カトリック)であったからである。欧米人たちは、キリスト教徒が少数派(註:インドネシア内では圧倒的に少数派)として苛められていると彼らが認識した際には、早急に行動を起こす。ボスニア・ヘルツェゴビナでの内戦の時にも、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国を構成する3つの民族(註:言語的には、ほとんどひとつの民族であるにもかかわらず)のうち、セルビア人については、セルビア正教徒であり、同じスラブ系ということで、ロシアがこれを支援し、イタリアに近いクロアチア人は、カトリック教徒であるということで、欧米諸国が支援した。そして、イスラム教徒であるが故に、欧米からの支援を得ることができなかったモスレム人たちが一番酷い目に遭っていたが、欧米諸国の誰も彼らを助けようとせずに、結果的には、イスラム諸国から義勇軍(註:こういう勢力がタリバンやムジャヒディンの温床になる)が馳せ参じて、三ツ巴の内戦が行なわれたことは記憶に新しい。同様のことが、今年5月にインドネシアから「独立」を果した東ティモールにおいても言えるのである。いつも、国際社会から「人間扱い」されるのはキリスト教徒だけなのである。(註:同じインドネシアからの独立運動でも、アチェ特別州の場合、イスラム対イスラムという構造なので、欧米諸国からの支援は受けられず、こういう状況がアルカイダなどに活動の場所を提供することになる)
▼細身の乙女と大勢の僧侶
しかし、今回の私のテーマは、あくまでジャワ島の風土と宗教についてであるので、本件についてはこれ以上、深く触れない。私は、メガワティ・スカルノプリ大統領も臨席して開催された第6回ACRP大会の開会式に出席した(私と同じ列の5〜6人分離れたすぐ近くの席に座られたので、警備がものものしかった)が、開会式の演出からして、(分離独立問題で騒しい)アチェ特別州(スマトラ島北部)、ジャワ島、カリマンタン島、そして、東の端のパプア島(ニューギニア)まで、多彩な歴史的・文化的背景の異なった人々が暮す国であるインドネシアが、民族と宗教の「和解」ということに対して大変な気を使っていることを知ることができた。今回のACRP大会のテーマも、この「和解」ということが強調された。会議の内容はマニアックで面白くないので、会議の合間を縫って、このジョグジャカルタ市のはずれにあるヒンズー教の遺跡プランバナンを訪れた時の印象から記したい。
東南アジアの場合、こういった有名な観光地の周りには、必ず、土産物売り(の子供たち)がたくさんいるが、その中を掻き分け掻き分けして進まないと、目的地に到達できない。プランバナンは、巨大な石造り(註:LEGOのように基本的な形の石を積み上げて造形する方式)の遺跡であった。しかも、入場料を支払って入った公園の入り口から肝心の遺跡までは相当の距離がある。途中にゴロゴロと転がっている崩れた石垣のようなものがたくさんあった。日本よりも活火山の多い地震国インドネシアで、ブロック造りの寺院を建立することにどだい無理がある。現地人のガイドに聞くと、「建造当時は、これらの広い地域すべてがプランバナンであったが、すべて倒壊してしまって、瓦礫の山となってしまったが、1973年から修復工事が始まった」らしい。石造りの尖塔の数は、元もと224基あったそうであるが、今は、わずかに再建された中心の3神殿とその付属建物だけでも、そこそこの規模なのだから、創建当時は、さぞかし壮麗な大伽藍だったのであろう。プランバナンという名称の由来を聞くと、「多い」という意味の「Para」と、僧侶(バラモン)という意味の「Brahmana」を合せた言葉で、つまり、「たくさんのお坊さん」という意味だそうである。
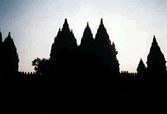
夕陽に浮かぶ摩天楼のようなプランバナン |
プランバナンの寺院群は、ピラミッドのような階層構造になっている。(夕陽に浮かぶシルエットは、まるでマンハッタンの摩天楼である)その中央には、220メートル四方の基台があり、その上に、3つの大きな尖塔を有する神殿が建っている。中央に聳え立つ、高さ約47メートルの最も高い神殿がシヴァ神殿(註:ヒンズー教の3人の最高神、すなわち、ブラフマ・ビシュヌ・シヴァのうちのひとり)が建っており、その中には、「ロロ・ジョグラン(細身の乙女=実際には、結構グラマラス)」と呼ばれるサンジャヤ朝ピカタン王の霊廟として建てられた祠堂がある。そして、シヴァ神殿の北側にちょうど半分の高さ(23メートル)のビシュヌ神殿、南側に同じ高さのブラフマ神殿が建っており、高さが正確に1:2:1の比率になっている3つの神殿自体が、東西方向から見ると、「三尊形式」を構成している。

プランバナン中央のシヴァ神殿 |
それぞれの神殿の対面には、三神の乗物(註:仏教やヒンズー教では「乗物」という概念が重要である)となる神獣(鳥)を祀った祠(ほこら)もある。因みに、インドネシア航空のマークにも採用されており、また日本の古典芸能の舞楽・伎楽で用いる釈楼羅(カルラ)面モデルにもなっているガルーダという鷲は、ビシュヌ神の乗物であるということになっている(註:因みに、ビシュヌ神の妃は日本で吉祥天として知られるラクシュミである。同じく、ブラフマ神の妃は弁財天として知られるサラスヴァティーである)。ヒンズー教の神学においては、宇宙の根本的な法(ダルマ)であり創造者であるブラフマと、ものごとを維持発展させる神ビシュヌと、これらを破壊する神シヴァによるトリニティー(三位一体)構造として世界を理解しているが、それらの三神の内、最もポピュラーな神が破壊を司る神シヴァであるところが、諸行無常の世界観を持つインドの宗教らしいところである。
▼シヴァ・リンガとホモ・エレクトス
プランバナンは、ジャワ島において仏教が衰退した後、仏教の後を追うようにインドから拡大してきたヒンズー教徒たちによって造られた。そのシヴァ神を奉る中央神殿の基壇に浮き彫りにされたレリーフは、有名な叙事詩『ラーマヤナ』の物語を再現している。それにしても、余白というものを徹底的に嫌い、空間を大小様々な神・獣像で覆い尽くすヒンズー教のゴテゴテ感覚は、日本人の私には、少し食滞気味である。ヒンズー教とは正反対に、具象的な偶像を一切否定したイスラム教も、別の意味でヒンズー教と同様、余白というものを嫌った。「アッラー(神)の完全性」を全うするためには、空間(無)はすべて埋め尽くされなければならず、偶像の代わりにアラビア語の壮麗なカリグラフ(書道)やモザイクの幾何学模様によって、モスクの壁が埋め尽くされているのが通例である。カリグラフこそは、象形の記号化と呼べるものではないか。あるいは、具象から抽象への進化ともいえる。

ゴテゴテしたレリーフで埋め尽くされた回廊の壁面 |
この具象の記号化のプロセスは、ヒンズー教の寺院においても違う形で存在した。ヒンズー教寺院において、神像の代わりとして、そこかしこを埋め尽くすシンボルとは、いったい何か? それは、たいていの場合、遠くから見れば、砲弾のような形をした石の物体である。具体的な神々の姿を穿(うが)った像より、極めてシンプルな形をした石造物である。これがいわゆるシヴァ・リンガ(男根)である。聖堂の内部においては、リンガがその受け皿となっている石臼のような形をした台ヨーニ(女陰)の上に置かれており、かつて、そこで生け贄が捧げられたであろうというような構造をとっている。本来、リンガとヨーニは、二つで一つの対をなすべきものであるはずであるが、実際にヒンズー教寺院を訪れてみると、至るところにリンガだけが単体で屹立している。まさに、大都市の摩天楼のように生命の原理をシンボライズして、それが天にも届かんという姿なのである。かつて私は、当「主幹の主観」シリーズの記念すべき第1作として、『神道と柱』という作品で、縄文時代以来続く、日本人の立柱信仰について述べたことがあるが、ここにも形を変えた立柱信仰があったのである。人間存在というものは、ともかく、東アフリカで類人猿が立ち上ったこと(直立二足歩行)から始まり、それ以来、常に天を目指して上へ上へとその成果を積み上げてきたのである。まさにその意味で、人類は「ホモ・エレクトス(直立するヒト)」なのである。

寺院のそこかしこに屹立するシヴァ・リンガ |
▼恐るべし「味の素」
私たちは、かつて東ジャワ王国を統治していた藩王=スルタン(註:現在でもこの地域に君臨しており、第2次大戦後のインドネシア共和国成立と共に、インドネシア共和国の一部に編入されたこの王国に対して、インドネシアの中央政府は特別の敬意を払い、そのスルタンを州知事に任命してきた)のハメンクブオノ10世に招かれて、その王宮でガムラン音楽の生演奏と晩餐会に招待された。スルタンはわれわれのために、FIFAワールドカップの韓国対ドイツの準々決勝の試合を生中継で視れるように、特別の手配もしてくれた。この気さくなスルタンは、町の人々からも敬愛されている様子で、由緒あるハメンクブオノ王家の伝統を継ぐスルタンであると同時に、地方行政府の長としての州知事でもあり、また、現在のメガワティ大統領とは幼なじみでもあるインドネシアの重要人物であるが、少しも「偉そがっている」感じがしなかった。プランバナンを見学したその足でディナーに合流した私は、服装を改める時間がなかったが、ポロシャツ姿の私にもスルタンは気さくに声をかけてくださった。

スルタン(左)に挨拶する三宅代表。右は、世界イスラム連盟のマルワット事務総長 |
現スルタンの父君であるハメンクブオノ9世は、戦後の民主主義をいち早く取り入れた君主であり、観光振興のために日光も訪れたこともあり、自ら厨房に立って料理もするという、欧米風の現代的なライフスタイルを好んだスルタンだったそうである。王宮内で、先代スルタンの記念館に行っていろいろな展示物を見たが、最も興味深かったのは、私が子供の頃にはまだ日本にもあった缶に入った「味の素」であった。先代のスルタンは、よほど「味の素」が好きだったと見えて、王の料理道具の非常に重要な位置に「味の素」の缶や瓶が並んでいたのには驚いたが、これも、この地を訪れる日本人観光客を意識しての演出とも考えられる。そう言えば、3年前、この国で起こった「味の素」騒動――すなわち、「味の素」の原料にイスラム教徒が食することを禁じられている豚から抽出されたエキスが入っているか、入っていないかで、国論を二分する政治的大問題となったこと――で、当時のアブドゥルラフマン・ワヒド大統領が仲裁に乗り出したことを思い出した。一説には、この時のワヒド大統領の仲裁方法が国民の不興を買い、「失脚」につながったという説もあるくらいだ。まさに「味の素恐るべし」である。

先代スルタン愛用の「味の素」
|
このスルタンの王宮に仕える家臣たちは、厳密に言えば実は家臣ではない。かつての王政時代には、まちがいなく家臣であったのであるが、現在も、主にその元家臣たちの子孫約1,600人が、王宮でボランタリーに「家臣の役」を務めているのである。何故、ボランティアであるかというと、1ヵ月間家臣を勤めてもらえる俸禄(給料)が、最高位の人でも7万ルピア、日本円で900円程度である。ほとんどの家臣は、1ヵ月200円程度の俸禄を頂戴しているだけ……。いくら物価の安いインドネシアでも、これではまったく生活をしてゆくことができない。そこで、別の仕事、あるいは生活に余裕のある人が、名誉職として王宮で「家臣の役」を勤めているのである。これもまた非常に奥深い、インドネシア的な風習だと思った。
▼ボロブドゥールは須弥山である
プランバナンを訪れた3日後、私は、ユネスコの世界文化遺産にも指定され、また、カンボジアのアンコールワットと共に「世界最大の仏教遺跡」と言われるボロブドゥール寺院を訪れた。ジョグジャカルタからバスで移動すること約1時間、ボロブドゥールはジャングルの中から突如、私の目の前に姿を現わした。一言で言えば、まるで「山」である。ガイドの説明によると、1辺が約120メートル四方の基壇の上に、9層(段)の回廊が設けられたピラミッド状の構造物である。下の6層が真四角で、上部の3層が円形という「上円下方噴」と同じ形態(註:古代中国でも、「天は丸く地は四角い」と考えられていたので、古墳の形もこうなった)である。基壇の部分の回廊の壁には、釈迦の前世の物語をテーマに描かれた『本生譚(ほんじょうたん)』のレリーフが施されている。この巨大な仏教遺跡(もちろん、建造当時は礼拝の場であった)は、8世紀末から9世紀初めにかけて、シャイレーンドラ朝の時代に造られた。

ボロブドゥールの基壇に描かれた『本生譚』のレリーフ |
しかも、驚くべきことに、当時この国で流布した仏教は、日本と同じ大乗(マハーヤナ)仏教であった。インドで誕生した仏教は、スリランカあるいはビルマからタイへと至るコースで拡大していった流れを上座部(テーラバーダ)仏教(あるいはその伝播のコースによって、南伝仏教と呼ばれる)と呼び、インドからチベット、西域諸国、中国、朝鮮半島、日本へと伝わった大乗仏教(伝播ルートから北伝仏教と呼ばれる)と呼ばれることが常識であるが、なぜだか、この南海のジャワ島には、上座部仏教ではなく、密教がかった大乗仏教が伝わったのである。このこと自体、非常に興味深いし、また、後の時代まで、仏教が残らずにヒンズー教に併合されていく原因ともなった。
さらに私の関心を惹くのは、ボロブドゥールの建造された時期である。8世紀末から9世紀初めといえば、日本では、桓武天皇による平安京遷都(及び、全国統一)と、空海や最澄が活躍し高野山や比叡山が開かれた時期と重なるのである。インドで始まった仏教が、本家のインドで急速に衰え、消滅して(註:密教化が進み民俗宗教のヒンズー教に呑み込まれていった)しまったにも関わらず、ユーラシア大陸の北東の島国日本と南東の端のジャワ島において、この時期、最も壮麗な寺院群が建てられたのである。このことの奇妙な一致が大変気になる。金剛峯寺(高野山)や延暦寺(比叡山)は何故、街中ではなく山の上に建てられたのであろうか? あるいは、実際に山上に建立されなくても、仏教寺院の正式名称は「○○山××寺」と呼ばれることの本当の意味は、何なのであろうか?

ボロブドゥールの上層3段に安置されたストゥーパ群 |
「空」を説く仏教でありながら、ゴテゴテのレリーフで埋め尽くされた下段の方形部の6層と、上段の円壇部3層とは、まるで趣きが異なる。上層の円壇部には西欧の教会堂にある釣鐘のような形をしたブロックで造られた小さめのストゥーパ(卆塔婆=仏塔)が並んでいる。イチゴで飾りつけられた3段のデコレーションケーキをイメージすれば解り易いと思う。下の段(外側)から32基、24基、16基と、あたかも、原子核を周回する電子軌道モデルのように、合計72基の小さめのストゥーパが整然と並び、それらの中には、それぞれ、ほぼ等身大の仏が鎮座している。そして、最上段(中央)部分には、巨大なストゥーパ(これだけは、中が覗けない)が置かれているのである。ボロブドゥールのことを指してよく「巨大なストゥーパ」と言う人があるが、実際に、私がこの目で見た感覚では、仏教的宇宙観・世界像を表した須弥山(しゅみせん)モデルを、目に見える形で表現しようとしたものであると考えられる。つまり、6層の基壇があって、これらは、衆生の暮らす「六道輪廻」の世界であり、その上の3層が「悟り」へ至る道を表わしているものと推察できる。これらのピラミッド状の構造物は、それぞれの精神的なステージによって異なる世界が現されている。そして、それを一歩一歩階層的に昇ってゆくことによって、自然と涅槃(ねはん)の境地を目指すことができるのである。
▼仏教は階層的宗教である
私は、ACRP会議に参加したアジア各国の宗教指導者たち(イスラム教徒・ヒンズー教徒・キリスト教徒・仏教徒・ゾロアスター教徒等)と共に、この巨大な遺跡を巡った。そこで目にしたそれぞれの行動は、大変興味深いものであった。旧知のタイ国の高僧(彼と最初に出会ったのは、十年程前にニューヨークの国連本部である)が、お供を引き連れて悠然とこのボロブドゥールに登ってきた。東南アジアの観光地には、しつこすぎで、辟易とするだけの物売り(子供の場合も多い)が大勢いるが、同時に、裕福そうな観光客に対して、頼まれもしないのに勝手に日傘などを差しかけて来て、「臨時の家来」としてその人のお供をし、チップを貰うという輩もいるのであるが、身分制社会に慣れていない日本人などは、そのような行為には戸惑うのだけれども、身分制度を当たり前のこととしている社会(註:チップ制度のある国はすべて、ある意味での「身分制」社会であると考えてよい)に暮している人たちから見れば、そのような訳の判らない「勝手連的家来衆」に対するあしらいも、手慣れたものであると感心した。

件のタイ人僧とボロブドゥールの上層 |
そのタイの高僧は、お供の差し出す日傘の下を、一段一段、悠然と登ってきた。そして、円壇部に達した時、この世界的に有名な仏教遺跡であるボロブドゥールを訪れた記念に、一箇所だけあるストゥーパが壊れて中の仏陀の像が剥き出しになっている場所で、記念写真をそのお供の者に撮らせていた。通常、このような構造物は、大きすぎて、かなり後退しないと全体がカメラのフレームに収まらないのであるが、そのお供も、僧侶から差し出された最新式のデジカメを持って、僧侶と仏像のツーショットを撮ろうとしていた。事件はその時に起きた。僧侶と仏像のベストアングルを得るため、一歩二歩と後ずさりしていたその男が、ボロブドゥールの円壇のステージを踏み外して、2メートルほど落差のある下(外側)の壇まで落ちたのである。その瞬間は、あたかも電子が瞬時に隣の軌道へジャンプしたようで、一瞬、視界から消えた。もちろん周りは石だらけで、打ちどころが悪ければ生命にすら関わることも考えられる。その事件を目撃したその周りにいた世界各国から来ている観光客たちは、慌てて集まり、落ちた男に「大丈夫か?」と心配そうに声を掛けた。幸いたいしたケガはなかったようだ。そうこうしていると、悠然とその僧侶は上の壇からこちらを見下ろし、「カメラは大丈夫だったか?」とだけ聞いて、次の壇へさっさと上がって行ったのである。上座部仏教の持つ身分社会的要素を、象徴的に見た気がした。
▼人間の手で「山」を造る営み
他にも、このボロブドゥール遺跡には、天台宗の西郊宗務総長をはじめ、日本人も何人か来ていたので、それぞれに興味深い話がたくさん聞くことができた。中でも、今回の旅行中『ダメおやじ』で有名な漫画家の古谷三敏氏と知己を得て「原作三宅善信、画古谷三敏で新作を発表しないか」というところまで話が盛り上がった。ジャワ島のイスラム教化によって放棄され、千年間密林の中に忘れ去られていたこの遺跡は、1814年大英帝国のジャワ総督ラッフルズによって、偶然、ジャングルの中から発見されたのである。その後、オランダのジャワ統治下で「発掘」が進んだ。英国の総督ラッフルズは、また、シンガポールの「建国の父」でもあり(註:それ故、圧倒的に中国系住民の多いシンガポールの公用語が英語になった)、現在、シンガポール航空のビジネスクラスにその名を残すほど、この地域ではプレステージの高い人物になっている。

『ダメおやじ』の古谷三敏氏と意気投合して |
ボロブドゥール遺跡は、20世紀に入って、オランダの植民地軍が本格的な修復作業を開始したが、インドネシアの独立と共にこの世界的文化遺産は再び放置(註:偶像を嫌うイスラム教政権が、このような文化財を保護しないのは、2001年3月のタリバン政府によるバーミヤン仏教遺跡の破壊を見るまでもない)され、やっと1973年から83年にかけて、ユネスコの手にによる修復作業が行なわれたのである。驚くべきことに、ユネスコは10年の歳月を掛けて、すべての石に番号を付け、遺跡を完全に解体し、いったんデータベース化した後に、雨水による侵食防止処置等を施して、再びボロブドゥールが構築されたのである。

ボロブドゥール寺院は、まるで「ひとつの山」 |
ジャワ島は、日本列島以上の火山島であり、私が宿泊したホテルの窓からも、熱帯雨林の遥か彼方に、ちょうど新幹線から富士山が望めるような感じで、富士山と同じくらいの姿形をした活火山のスメル山を見上げることができた。日本には、富士山クラスの山はひとつしかない(註:それ故「不二」山の別称がある)が、ジャワ島には最高峰のブロモ山をはじめ富士山クラスのコニーデ型火山がいくつもあって、壮観である。しかも、そのほとんどが活火山である。火山の頂きはその高さ故、雲に隠れ、晴れている時には頂きから噴き出す噴煙が力強く、いかにも神々しい感じがする。初めてこの島に人類(ジャワ原人)が足跡を残してから20万年以上の時間が経過しているが、その間、人々は、これらの山々に、神々の存在を感じたことであろう。ヒンズー教寺院のプランバナンといい、仏教寺院のボロブドゥールといい、この島において石造りの巨大宗教建築が造られたのは、その意味で、まさに「人の手で山を造る営み」であったと言える。因みに、ブロモ山のブロモとは、ヒンズー教の最高神ブラフマの訛ったものであり、スメル山のスメルとは、言うまでもなく宇宙の中心に聳え立つ須弥山のことである。

どう見ても富士山に見えてしまうスメル山 |