レルネット主幹 三宅善信
▼God Save Our Queen
私は、「政権を選択する選挙」の前日(11月8日)か会議に出席するため、英国に出張(註:もちろん、不在者投票は済まして)した。英国に到着したその日は、夜も遅かったので、とりあえずオックスフォード市内の小さなB&B(註:「ベッドと朝食だけの安宿」という意味)に泊った。当然のことながら、この手の宿屋には衛星放送などという気の利いた設備はないので、勢い地元のローカル放送を何気なく(註:外国人である私にとって、CNN等の「世界のニュース」なら見る意味があるが、ほんの3日間だけ滞在する英国の、しかもローカルな番組を視ても、ほとんど自分自身の生活にとって意味がない)を眺めていていたら、何やら、サーカスでもできそうな中央が土間になった大きなオーバル(註:楕円形の室内スタジアム)の観客席に、年老いた善男善女が大勢集まっているイベントの様子が放映されていた。
画面を視ていると、勇ましい鼓笛隊のマーチに乗って、兵隊とおぼしき人たちが、あちらこちらの階段から数人ずつのグループに分かれて(中央の広間へ)入場してくるのである。これがまた面白いことに、おそらく、それぞれの軍隊が成立した当時の制服を着ているので、20世紀の中頃になってから編成された空軍を除けば、他の兵隊さんは皆、まるで芝居(時代劇)の中のような格好(註:極めて非実戦的)である。海軍といったら、まるで『ポパイ』の水兵さんの格好だし、看護婦(註:近頃、日本では、ジェンダーの問題もあって、看護婦のことを看護師と言い換えるようになったが、どう考えても納得できないのは、看護師の「師」が、気象予報士の「士」ではなくて、医師の「師」という字が使われているところである。これなら、呼びかける時にも「看護婦さん」ではなくて、「先生」って言わなければならなくなってしまう。ナースはドクターではないのであるから、やはり「師」はないと思う)なんか、まるでナイチンゲールの物語に出てくるような頭巾を被っている(まるで、小学生の給食当番)のには笑ってしまう。そして、なんと言っても、一番歴史が古いのは、どこの国でも陸軍である。大英帝国陸軍(Royal
Army)の儀仗用の正装は、言うまでもなくバッキンガム宮殿の衛兵でお慣みの真っ黒けの大きな帽子をほとんど前が見えないくらいに深々と被った赤い服を着た兵隊である。その上、ボーイスカウトの少年たちも入場してきた。よく見ると、観客席の老人たちはみな、胸に(日本の「赤い羽根」みたいな)赤い花(ポピー=けしの花)を象ったバッジを付けていた。
その日は疲れていたし、延々と入場行進ばかり続いていたので、さして意味も考えず数分でテレビを消したが、翌朝テレビを点けると、さすがに日曜日の朝というか、どのチャンネルも、まじめなニュース番組なんぞオンエアしている局はひとつもなく、ローカル局は皆、サッカーのプレミア・リーグの試合ばかりで、国営放送のBBCは、オーストラリアで開催中のワールドカップ・ラグビーのイングランド対アイルランドの試合が始まるところを中継していた。もちろん、この試合は国際大会であるからして、最初に両国の「国歌」が斉唱されるのであるが、日本の場合には、観客はもとより「日の丸」の付いたユニフォーム(註:ナショナルチームの「National」とは「民族の代表」という意味であることは言うまでもない)を着ている選手でも、実際に声を出して『君が代』を歌う人はあまりいないように思われるが、各民族のナショナリズム丸出しの「五カ国対抗リーグ戦(Five
Nations)」のメンバー同士(註:ラグビーでもサッカーでも、その国際競技連盟成立時に、既に競技が盛んに行われていた「英国(United
Kingdom)」内の各ナショナルチームがそれぞれ独自に連盟に加盟したため、「連合王国(United kingdom)」を構成するイングランド・ウェールズ・スコットランドは、それぞれ「別の国」扱いになっている。因みに「5カ国対抗リーグ」の他の2チームとは、アイルランドとフランスである)の組み合わせのせいか、イングランドチームの国歌斉唱の際には、選手はもちろんのこと、わざわざ応援に駆けつけた観客も皆大きな声で『God
Save Our Queen』を歌っている姿が印象的であった。
▼「多様な宗教の平和的共存」こそ日本の価値
私はゲーム最初の数分間を視た後、迎えが来たのでホテルをチェックアウトし、車を走らせてオックスフォードからさらに約1時間ほどの距離にある長閑な(註:本当に周りには見渡す限りの畑と放牧された馬や羊しかいない)クエーカー教団(Quaker:その教義は「絶対平和主義」であり、敵に銃を向けることが許されないので、たとえ徴兵されても彼らは兵隊にはなれず、アメリカや英国においては、クエーカー教徒の場合は、「良心的兵役拒否(Conscientious
Objection)」といって「徴兵に応じなくてもよい(その代わりに、きつい社会奉仕活動をする)」という権利が法律で認められているほどの社会的に認知されたマイノリティ教団)の研修施設で開催された国連経済社会理事会の諮問を受ける数少ないNGOのひとつIARF(国際自由宗教連盟)の執行理事会に出席した。
私は、1981年にオランダのライデン近郊で開催された第24回世界大会に参加して以来、24年間にわたってこの団体とは関わりを持っている。特に、昨年(2002年)ハンガリーのブダペストで開催された第31回世界大会の際に、世界中で17人しかいない評議員(任期4年)のひとりに選任されたが、そのずっと以前から、亡祖父や父も同団体の役員を務めていたので、その随行や名代として、1980年代以後ほとんどの執行理事会や評議員会に出席していたので、現職の会長や事務総長を含めて現存する他の国際役員の誰よりも多くこの団体の役員会には出席している。私は、この団体以外にも、いくつかの国際NGOの海外での役員会に、この四半世紀の間に百回以上参加しているので、ある意味この分野(諸宗教間対話)における経験で、私の右に出るものは、世界中でもごく僅かだと思う。
ところが、「多様な諸宗教の平和的共存」という世界的にも掛け替えのない歴史的・社会的価値を持ちながら、日本政府同様、「財的貢献」にしか発想が行かない宗教団体が日本に多いのは何故だろうか? こういった状況に渇を入れるべく、ひとり気を吐いている私であるが、欧米の国々から選ばれた役員たちは、未だに日本からは、その「多様な諸宗教の平和的共存」という社会のあり方を手本にしようというよりも、単に財的貢献しか期待されていないのには、明治以後の国際会議に出てきた大多数の日本人の態度にも責任があると思う。
現在、この団体(註:この団体だけでなく、欧米の非営利法人すべてについて一般的に言える法則でもある)が抱えている多くの問題は、既に10年以上前の役員会で私が反対したことを押し切って多数決で役員会が決議したことばかりであり、私の言った通り、現実が裏目に出たにも関わらず、執行部は積極的に責任を取ろう(例えば。総辞職)とはせず(註:近代民法における財団法人は、株式会社と同様「有限責任(Company
Limited)」であるため、経営判断の甘さによって法人に多大な損失が生じても、役員個人が経済的責任を負わなくてもよいようになっている)、それを「外的要因のせいだ」という。私は、10年前に今日の姿を予見して反対論を唱えたが、彼らにとっては、私の現状分析と将来予測が「正しかったか」どうかではなく、その意見が「多数派であったか」どうかが価値判断基準になっている以上、そして、私が現在においてもなお少数派であるところに、日本のみならず、世界の救い難さがあるのが見て取れる。
▼ノートルダム大聖堂で英国兵が……
英国からの帰途、26年ぶりにパリに立ち寄った。シャルル・ド・ゴール空港は、毎年、乗り継ぎで何度も利用するが、いわゆる「観光地」という所にはあまり足を運ばない私であるので、同じヨーロッパの都市でも、会議がよく行われるオックスフォードやフランクフルトには既に20回以上足を運んでいるにも関わらず、どういうわけかパリの街には縁が薄かった。というより、やはり国際会議は、たいていの場合、公用語が英語であるため、会議場の中だけでなく、ホテルやレストランなど街全体が英語があまり通じないイメージのあるフランスで開かれることが少ないからであろう。
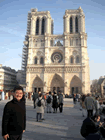
ノートルダム大聖堂の前で |
今回、ド・ゴール空港からパリ市内まで、たまたま乗ったタクシーの運転手が元カンボジア難民だった(註:いうまでもなく、ベトナムとカンボジアはフランスの元植民地だったため、フランス語を解する人々が結構いる)ので、彼らのフランスでの暮らしなどを話題にしながら、車を飛ばしたが、つくづくブルボン王朝の絶対王制やナポレオン帝政(ナポレオン3世も含めて)抜きには、この美しい都市は絶対に造れなかったであろう(註:個人の人権や自由などに配慮していては、そもそも、大規模な都市計画などというものは成り立たないのである)。見事なまでのパリの街並みを車窓から眺めていたら、おそらく百年経ったら見るべき価値なんぞ無くなっているであろう単なるビルばかりの街しか造れないアメリカ人の言うことなんか青臭くって、聞く気になれないフランス人のエスプリが解るような気がした。街の看板や表示のどこにも英語がないところが気が利いている(註:日本では、すべての公的案内表示には、必ず英語表記が併記されているだけでなく、わが大阪市なんぞ、ご丁寧にもハングルと北京語まで表記されている。これではまるで、「植民地」である)。これなら、日本人以上に外国語が苦手なアメリカ人も困るだろう。残念ながら、これまでフランス語を習う機会がなかった私であるが、学生時代、英語とドイツ語以外に、ギリシャ語やラテン語といった古典語(ついでにヘブライ語も)を習う機会があったので、欧州圏の言葉は、全く起源の異なるフィン(エストニアとフィンランド)語とマジャール(ハンガリー)語を除けば、読めば一応、なんとなく意味が解るので、その点、事前に思っていたほど苦労はしなかった。

聖堂の回りには警察の物々しい警備が… |
少し時間があったのでノートルダム大聖堂を覗いて見た。聖堂前の広場には警察が物々しい警備をしていたので、万事テロ流行りで、「このような観光地まで物騒なご時世になったこと」と思っていたが、聖堂の中に一歩踏み入れて、もっと驚いた。まさに、ミサが行なわれている最中であったのであるが、フランスでは耳障りなほど大きな声の英語でミサが行なわれているのである。しかも、「心の貧しき者は幸いなり」で始まる有名な『マタイによる福音書』第5章のいわゆる『山上の垂訓』である。司祭の説教を何気なく聞きながら聖堂の入り口付近から前の祭壇のほうに進んで行くと、襟首にカラーを着けたお馴染みのカトリックの司祭(神父)たちではなく、例の真っ赤な制服に黒い毛むくじゃらの高い帽子を被ったあのバッキンガム宮殿にいる儀仗兵と同じ英国スタイルの兵隊たちがたくさん司祭の席にいた。

聖堂内では、退役軍人に混じって
ボーイスカウトも
|
さらに説教の内容に耳を傾けると、どうやら、第一次世界大戦の終戦記念の追悼ミサを行なっているようである。会衆の多くは老人たちであるが、中には第一次世界大戦とは縁もゆかりもなさそうなボーイスカウトの少年たちもたくさんいるのである。ここで気が付いた。日本では、何気なく「ボーイスカウト」、「ガールスカウト」と言っているが、英語では「boy
scout」すなわち「少年による斥候(せっこう=偵察)兵」のことではないか(因みに、ガールスカウトは、英語では「girl
guide」と呼ばれる)。今では、欧米各国は、中東やアフリカにおける少年兵のことを批判しているが、百年前には、自分たちも年端もいかない、善悪の判断もままならない少年を、しかも最も危険な斥候として使っていたではないかと思うと腹が立ってきたが、よく考えてみると、11月11日は、飛行機・戦車・毒ガス等の大量破壊兵器が人類史上はじめて実戦で使用され、欧州では非戦闘員の一般市民も含めて1,000万人以上の犠牲者を出した第一次世界大戦の終戦記念日(Remembrance
Day=追悼の日)であった。1918年の11月11日の11時を期して戦争が終ったのである。
▼唯一の神に戦勝を祈るという論理的矛盾
ホテルに戻ってCNNにチャンネルを合わせてみると、ちょうど英国では、エリザベス女王とオーストラリアのハワード首相が並んで、第一次世界大戦の戦没者慰霊の式典(註:第一次世界大戦における英国軍の戦死者数は95万人にのぼった。全参戦国の将兵の戦死者数は850万人!)が行なわれていた。また、米国では、この日のことを「Veteran’s
Day(退役軍人の日)」と呼んでいるが、欧州のそれより、もっと物々しい式典が行なわれ、ブッシュ大統領がアーリントン国立墓地で英霊(戦争で殉職した兵隊のこと)に花束を捧げ、儀式用の軍服を着たテノールが、声高らかに「♪God
Save America. My Home Sweet Home♪」と唱い上げていた。続いて行なわれたブッシュ大統領によるスピーチも、この八十数年前の戦争で犠牲になったアメリカ兵22万人の話ではなく、この一両年の間に行なわれたアフガニスタン戦争とイラク戦争での数百人の犠牲者を追悼する内容であった。しかも、「勇敢なアメリカ人の若者が、可哀想なアフガン人やイラク人のために、自らのいのちを懸けて、その独裁者を滅ぼしてやったことが、神によって託されたいかに崇高なアメリカの使命に叶ったことであり、これからもたくさんの犠牲者が出るだろうが、アメリカは必ずそれらをやり遂げる!
May God Bless America. May God Bless Veterans.」と言って、万雷の拍手の中、スピーチを終えたのである。
そうである。私が最初に英国に着いた翌日、イングランド対アイルランドのラグビー試合で聞いた「God Save Our Queen」も、また、この日、テレビで聞いた「May
God Bless America」も同じ論理から出たものであったのである。そもそも、読者の皆さんは矛盾を感じないか? 日本のように、はじめから八百万(やおよろず)の神々がおわすのなら、一人一人の、あるいは一国一国の願いを聞き入れてくれる神があってもおかしくないが、キリスト教やイスラム教のように、そもそも唯一の神しか存在しないというのであれば、現実に世界には200ほどの国があり、「それぞれの国がそれぞれの国を唯一の神が救うように願う」というのであれば――もし、英国と米国が戦争したとして、相方が「God
Save Our Queen」あるいは「May God Bless America」と祈った場合、唯一の神(God)としては、その唯一性故に、必ずどちらか一方が願ったことへの約束を果たせないことになり、「唯一であり、全能である」という神(God)の大前提が崩れるとは思わないのであろうか? あるいは、そのことからして、はじめから「唯一であり、全能である」というような神(God)の作業仮説は論理的に成り立ち得ないとは考えないのであろうか? そのことからして、私はこれらの人たちと相容れないものがある。
▼ 日本がアラブ世界で失うもの
その後のニュースは、イラクでの自爆テロによって、「初めてイタリア軍の駐留部隊に17人の犠牲者が出た」というショッキングなニュースであった。というのも、「そもそも、イラク人にとっての敵は、米英両国であり、それ以外のお付き合いでイラク占領に派兵している国は皆、自分ところはノーマークの安全牌」と思い込んでいた節(註:日本政府も同類で、「ここでイラクへ自衛隊を派遣すれば、アメリカに貸しを作るだけでなく、日頃から口うるさい日本の周辺諸国へもある意味、ブラフになる」と思って、早々にイラクへの形式的派遣を決定したのだ)があるからだ。
CNNのニュースは、1991年の湾岸戦争と2003年のイラク戦争とを比較して、湾岸戦争時に多国籍軍を形成して参戦した国が34カ国であるのに対して、今回のアメリカ主導のイラク戦争後のイラク占領に参加している国も32カ国と、ほとんど参戦国の数の上では変わっていないが、米ソ冷戦期以来、伝統的にアメリカの有力な同盟国であったG7のフランス・ドイツ・カナダなどが今回は抜けていること。その代わりに、ポーランドやウクライナといった国力ではほとんど取るに足らない国々が、数の上での帳尻合わせで派兵していることについて指摘していた。また、湾岸戦争の際には、米軍以外の多国籍軍の総兵力は、アラブ諸国からの兵隊も含めて25万人が参戦したが、今回は、30カ国合わせてもわずか28,000人という、極めて形式上の派兵であることを取り立て、いかにアメリカ一国が犠牲を払って困難な世界平和のために戦っているかというような自分勝手なコメントを流していた。
しかも、気になることに、「このたび(10月9日)の日本の総選挙によって、親米の小泉政権が国民からの付託を得た(選挙に勝った)ので、今後は日本の自衛隊も参戦する(註:日本政府は、在日米軍のために多大な駐留経費を支払い、憲法に接触してまで、個人の所有地を在日米軍の施設のために取り上げている(例えば、沖縄の「象の檻」)おり、日本国民は多大な犠牲を払っていることを、米国内のメディアを通じて十分宣伝していないので、アメリカ人一般は、「日本は安保にタダ乗りしている」と思っている)」ということを採り上げていた。国際的にはこのように見られている(註:アラブ側から見れば、先進国中唯一、キリスト教国でもなく、また、中東地域において唯一、植民地主義の手垢が付いていなかった日本が、長年かけて築いてきたアラブ諸国との信頼関係を捨て去ってアメリカの飼い犬に成り下がったと言う意味)ことによって失われる国益の大きさは測り知れない。そもそも。長くても数年間しかその座にいない総理大臣の個人的判断によって、過去の歴史を帳消しにし、将来何十年にわたる国運が左右されるというような決定をさせるということが間違っている。
いくら小泉政権が言うように、「非戦闘地域に自衛隊を展開する」といっても、そもそも、国際法に基づく正規軍同士の国際戦争ではないゲリラ戦に、非戦闘地域などあろうはずもなく、常に、人間の居るところこそが戦闘地域になる(無人の砂漠に向って銃を撃つバカはいない)のだ。しかも、非戦闘員のシビリアン(文民)である国際赤十字や国連の職員までもが「テロの攻撃対象」となっているイラクにおいて、誰の目にもミリタリー(軍人)にしか映らない自衛隊員が、「イラクの人々の衛生的な飲み水を確保するために駐留するのだから、テロの対象にならない」と考えるほうがどうかしている。こちらの善意なんか関係ない。
イラク人からすれば、巡航ミサイルやステレス爆撃機による空からの攻撃には、口悔しいながらも手も足も出なかったが、こうして敵が、自分の目の前に二本の足で立ってくれさえすれば、敵と自分とは1対1の互角の勝負である。しかも、こちらは、自らのいのちを的に戦う(自爆テロ)ことすら厭わないのであるから、負ける気がしないというのは当然のことだろう。独裁者であったフセイン氏を恨んでいるかいないかは別としても、大抵のイラク人は、家族や知人の一人や二人は、この十年間のアメリカによる空爆で亡くしているだろうから、アメリカ人に対して(当然、その手先となっている外国人に対しても)恨みに思うことはあっても、「フセインの圧政から自分たちも解放してくれた」と感謝しているはずはない。
▼真正面から取り上げなければならない慰霊の形
もし、そんな所へ「戦争しない軍隊」である自衛隊員がのこのこ出て行って犠牲が出たらどうするつもりなのか(註:この場合の犠牲というのは、自衛隊員が死ぬ場合だけでなく、テロ攻撃に応戦した自衛隊員によって殺されるイラク人も含めて)? 国家の命令によって戦地に赴き、尊いいのちを捧げたのであるから、当然、そのことへの報いは国家がしなければならない。しかも、それは単なる事故死(註:自衛隊においても、これまで相当数の隊員が「殉職」してきたが、それらのすべては、装備の故障や設備上の不良、操作ミスによる「事故死」等であって、敵と闘って死ぬ「戦死」とは、全く次元が異なる)のように、交通事故の際における保険金のように「金○千万円也」で済まされるものではない。それでは、死んだ当人も、大切な家族の一員を亡くした者も、納得できないではないか!
「戦死」には大義名分が要るのである。当然、英国やフランスやアメリカが行なっているように、国家元首による死者への賞賛と慰霊が行なわなければならないことは言うまでもない。所轄庁の役人風情による「追悼」などという生やさしいものでは済まされない。「追悼の辞」の奉読というものは、あくまで受動的な死者に対する慰めの形式であり、自らの命令によって死んだ者に対しては、このような受動的な慰めでは済まないことは言うまでもなく、積極的な意味での「慰霊」が行なわれなければならないことは言うまでもない。
こうなると、日本政府が1945年の終戦以後、60年間にわたって誤魔化してきた「国立追悼(慰霊)施設」の問題を、今度こそ真正面から採り上げざるを得ず、そのことは当然、「靖国問題」の決着も含めて、いつも何かと口やかましい周辺諸国を黙らせるだけの政治的手腕を伴うことであり、今回ばかりは小泉総理の小手先のパフォーマンス政治が通じないことは言うまでもないことである。短い期間であるが、英国とフランスを旅して、あらためて国家とその軍隊との関係について考えさせられた。