レルネット主幹 三宅善信
▼日本は人道支援のために開国した
ついに、自衛隊のイラク派遣(註:日本政府がどう国内向けに屁理屈を捏ねまわそうと、海外のメディアは「日本は第二次世界大戦後初めて、海外に軍隊を派遣することを決定した」と報じており、日本政府の狙いもまた、「一人勝ち」のアメリカの尻馬に乗って、周辺諸国が文句を付けられない状況下で「海外派兵」の実績を作ることにあるのは明白である)が決まり、小泉総理の会見でも、たびたび「日米同盟」という4文字が登場したが、そもそも、日本にとってアメリカ合衆国という国は、いかなる意味を持つ国であったのであろうか?
日本とアメリカ合衆国との関係が開かれて今年(2003年)でちょうど150周年を迎える。「太平の眠りを覚ます上喜撰(蒸気船)、たった四杯で夜も眠れず」という日本一有名な川柳で知られるペリー提督率いる4隻の“黒船”艦隊が嘉永6年(1853年)徳川幕府のお膝元江戸湾に現れ、湾内の航路測量を行うと共に、「祝砲」と称して威嚇射撃を行なったものだから、江戸の街は大騒ぎとなり、ペリー来航の幕府の対応がきっかけとなって、250年の長きにわたって盤石と思われていた徳川幕藩体制が一挙に解体へと向かって動き出していった「ラストサムライ」への始まりであった。
 ペリー提督
ペリー提督 |
言葉を換えれば、アメリカ合衆国との出会いが、日本の近代国民国家への転換の大きな要因となったのである。日本の近代史を考える時、良い意味でも悪い意味でも、その転換点には必ず、アメリカ合衆国という国が大きな影を落としているのである。その最初の出来事が1853年のペリー来航であり、次ぎに1918年(大正7年)のシベリア出兵、さらに1945年(昭和20年)の太平洋戦争終結とアメリカによる日本占領、そして、2003年(平成15年)の自衛隊のイラク派遣…。そのすべての原点が、この嘉永6年のペリー来航に始まるのである。
合衆国東インド艦隊司令長官であったマシュー・ペリー(Matthew Perry)は、第13代大統領のミラード・フィルモア(Millard
Fillmore)から日本皇帝(註:「天皇」は日本国内での呼称であって、国際的には、江戸時代はもとより明治時代になっても「皇帝(Emperor)」と外国からは呼ばれ、また日本政府自身もそのように自称していた)への親書を携えており、幕府に対して「日米修好(=鎖国政策の放棄)」を迫り、水や食料、石炭の補給などの「人道的支援」を認めさせたのである。
もちろんのこと、200年にわたる「鎖国政策」を採っていた徳川幕府にとって、このことは大きな矛盾をもたらした(註:もちろん、激動する国際情勢どころか世情からさえ隔絶した京の都の「禁裏」の深窓で、古色蒼然たる生活を送っていた公武協調路線の孝明天皇は、圧倒的な欧米列強の技術力や軍事力など想像だにできなかったので、この事態に対して観念的な「攘夷」論を展開したが、その攘夷論と反幕府勢力とが結びついて「王政復古」運動へと展開して行くことになろうとは、誰も思わなかった)。しかも、ペリーが日本に来た(註:日本本土に来る前に、琉球や小笠原を訪れ、現地の役人とも外交交渉を行なっている)最大の理由は、アジア(中国大陸)への展開をめざす米国東洋艦隊の補給基地として日本いくつかの港の開港を要求したのである(註:このこと自体、現在日本各地に米軍が基地を置いていることとほとんど同じ状況であるのは興味深い)が、そもそも、当時のアメリカの民間船が、はるか西太平洋の日本まで来るようになったのは捕鯨が主な目的であったと言うこと自身、ギャグ的である。
▼ペリー提督が飲んだ日本酒
しかし、当時の幕府はもちろん、現在の日本政府同様にマキャベリズム的「外交」交渉というものが、ほとんどまともにできていなかったことはいうまでもない。ペリー提督は、この嘉永6年と、大統領から日本皇帝への親書の返書を求めて、翌嘉永7年(=安政元年)の2度にわたって大艦隊を率いて江戸湾に来航しているが、当初、幕府の交渉担当となったのは、一地方役人の浦賀奉行(所の一与力)であり、2度目の来航の時に、やっと中央官僚である林大学頭(註:このような儒者を米国との交渉に当てること自体ナンセンスであるが、江戸時代を通じて幕府と国交があった朝鮮通信使の饗応の延長線で考えたのであろう)であったことからして、幕閣の事態対応能力が疑われる。
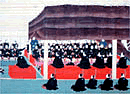 ペリー提督を招いた
ペリー提督を招いた
幕府主催の 晩餐会 |
要するに、なんのかんのと理由を付けて、ただ開港する時期を遅らせたり、あるいは開港する港の数を減らそうとした。これなんかまるで、現在の「日米農産物交渉」と同じだ。たとえば、「将軍が病気療養中である」とか、ほとんど外交交渉としては意味のない、むしろ統治能力を疑わせるような理由で…。しかし、次の年(嘉永7年)も現れたペリーに艦隊によって、彼我の圧倒的な軍事力や技術力の差を見せつけられて(例えば、蒸気機関車や電信機を見せられた)日本は、ついにアメリカに屈して鎖国を解いたのであるが、『日米和親条約』締結の際の晩餐会に饗せられたメニューが今に伝わっている。
 「鞆の祇園宮」こと
「鞆の祇園宮」こと
沼名前神社に 参詣して |
そのメニュー(註:基本的には懐石料理のフルコースと考えてよい)の中に「保命酒」という備後国(広島県福山市)鞆(とも)の浦の地酒が入っているのを知って私は驚いた。保命酒は日本最古の薬酒(註:有名な「養命酒」は、明治になってから、この「保命酒」を真似て醸造された)として知られている。国政の中心地であった畿内と、大陸・半島への玄関口であった太宰府を結ぶ古代瀬戸内航路の重要な中継地鞆の浦は、神功皇后の三韓征伐の神話や、代表的万葉歌人のひとり大伴旅人が太宰府長官から帰京する際に立ち寄って詠んだ和歌にも登場する瀬戸内交通の要所であった。同地には、疱瘡(ほうそう=天然痘)をはじめとする伝染病避けの神として尊崇を集めた「鞆の祇園宮」(註:京都の「祇園さん」として名高い八坂神社は、この沼名前神社から分祀されたそうだ)と呼ばれた沼名前(ぬなくま)神社(式内社)が鎮座している。
医療技術が進歩した現在でも、AIDSやSARSをはじめとし、人口が集約した都市文明を営む人類にとって大きな脅威である伝染病(感染症)は、科学的な知識がなかった古代の人々にとっては、何よりも恐れられていたことはいうまでもない。「科学技術の時代」と言われた20世紀に至っても、第一次世界大戦と同じ時期(1910年代)にヨーロッパから各地に感染が拡がったインフルエンザの一種「スペイン風邪」においては、なんと全世界で2,500万もの人々がいのちを落としているのである。この数は、毒ガス・航空機・戦車という大量破壊兵器が人類史に初めて投入された第一次世界大戦の総戦死者数850万人の実に3倍にもなる。
▼伝染病避けの薬酒として
この恐ろしい伝染病をいかに避けるかということは、常に民衆の最大の関心事(註:本テーマについては、拙論『都市と伝染病と宗教の三角関係』に詳解されているので参照されたい)であり、京都に千年の都が置かれるようになった時、朝廷が特に崇敬したのは、上下の賀茂社であり、また後の武家政権との関係によって石清水八幡宮であったが、なんといっても京都の庶民の信仰を集めていたのは、「祇園さん」で知られる現在の八坂神社(註:『神仏判然令』の出る明治維新までは、八坂神社は「祇園社」と呼ばれ、ご祭神も、明治以後に比定(ひじょう)された素戔嗚尊(スサノヲ)とその配偶神ではなく、道教的色彩の強い牛頭天王(ゴズテンノウ)とその眷属(けんぞく)たちであった)である。伝染病が最も心配される真夏の盛りに行われる祇園祭の際に、伝染病避けの呪いとして「粽(ちまき)」が配られた。

ミツボシ保命酒岡本亀太郎本店
6代目当主と筆者 |
この沼名前神社においても、鞆の浦の地酒である保命酒が御神酒(おみき)とされたので、民衆には「保命酒は伝染病に効く薬酒だ」と広く信じられていた。その保命酒が、あろうことか、ペリー一行を饗応しての幕府(日本政府)主催の晩餐会で供せられたというのである。ペリーだけでなく、その数年後に『日米修好通商条約』が締結された時にも、ハリス公使を招いた晩餐会の席でも、同じく日本を代表する酒として、保命酒が供せられているのである。紅毛碧眼の異人が持たらすであろう伝染病(註:事実、ヨーロッパ人からは「インディオ」と呼ばれたアメリカ大陸の先住民たちの多くの部族が、白人との闘いによってだけでなく、白人の持ち込んだ彼らには免疫のなかった伝染病によって絶滅した)を恐れたのか恐れなかったのかは知らないが、当時、幕府の筆頭老中の職にあった阿部備中守正弘の領国が福山であり、福山藩は江戸時代を通じて、この「保命酒」を専売品として全国に販売する権利(註:実際には、大名間の贈答に用いれた)を幕府から得ていたのである。ペリー来航によって混乱した国内政治が収拾するようにとの願いを込めて、嘉永7年には元号が改められて安政元年(1854年)となった。
▼金光教祖と保命酒
この同じ年(安政元年)の暮(12月25日)に、後(安政6年)に金光教の教祖となった備中国浅口郡大谷村の百姓赤沢文治(=金光大神)は、五男(宅吉、後の二代金光四神)の誕生に際し、当時の習俗では「四十二歳の二つ子(註:父が数え年42歳の厄年の時に、数え年2歳の子供がいること)悪し」と言われた(註:当時の年齢の数え方では、産まれた時が1歳で、最初のお正月が来れば数え年2歳になるので、12月25日産まれの人は、わずか生後1週間で2歳になってしまう)験を担いで、翌年(安政2年)の1月2日に生まれたことにして、名前も卯年に因んで赤沢宇之丞と名付けた。そして、正月4日に疱瘡避けで有名であった大谷村から西方へ約30km離れた鞆の祇園宮に参拝するのである(註:金光大神は、当時の平均的な日本人同様、授かった8人の子供の内、3人を幼少期に伝染病等で亡くしていたから)。また、同じ月の14日に自らの厄祓を祈願して、これまた、当方へ約30kmの距離がある備中国の吉備津神社へお参りして「おどうじ」(註:本テーマについては、拙論『桃太郎とは何者なのか?』に詳解されているので参照されたい)を受けている。
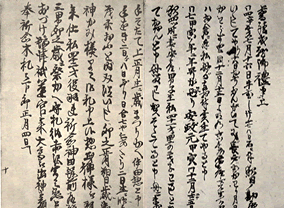 この辺りの経緯について記載されている
この辺りの経緯について記載されている
『金光大神御覚書』の当該箇所の一部 |
鞆の祇園宮に参った金光大神は、その度にこの「保命酒」を授かっているのである。その後も、神からの「お知らせ」を書き留めた金光大神の「お筆先き」ともいえる『お知らせ事覚帳』(安政4(1857)年から明治16(1883)年まで書き綴られた忘備録)や、これをもとに明治7年から9年にかけて再執筆された『金光大神御覚書』(文化11(1814)年から明治9(1876)年までの金光大神の生涯に起こったことの自叙伝)等においても度々、鞆の祇園宮のことが触れられているのである。盤石に見えた徳川幕藩体制がものの見事に瓦解したのを目の当たりにした金光大神は、朝礼暮改の明治維新政府のことも全く信用していなかった。
天理教祖中山みきと同様、それまでの日本宗教のパターンであった「地域共同体の宗教」である神社神道や、「家の宗教」となってしまった宗派仏教ではない、「(全人類の)親神(おやがみ)」という新しい概念を導入することにより、封建社会でいろんな制約を受けていた人々を、いったん「各個人」という単位に解体し、それぞれの主体的な選択による「信仰による共同体」をめざすという、まさに近代主義的な宗教がこの時に初めて日本に成立したのである。結果的には、日本社会に近代をもたらせたペリー提督も飲んだ同じ瓶から汲み出したであろう保命酒を金光大神も飲み、この時代に日本の近代化への激動の年月を進んでいったのである。