レルネット主幹 三宅善信
▼否めない“脳力”の低下
本日で恙なく満50歳を迎えた。ちょうど十年前の今日、私はエッセイ集「主幹の主観」コーナーで『四十にして惑わず?
林住期に突入』を執筆した。あれから十年、よく続けることができたものだ。その間、レルネットの通算ヒット数は50万件を超えたから、毎年、のべ5万人が拙文を読んでくださっていることになり、出版物ならそんなに売れることはまずないであろうから、まさにインターネット様々である。十年前、私は『四十にして惑わず?
林住期に突入』において、「人間の能力40歳ピーク説」(下図参照)を展開したが、それから十年を経過して、「今でもそのように思うか?」と問われたら、やはり「Yes」と答えるであろう。
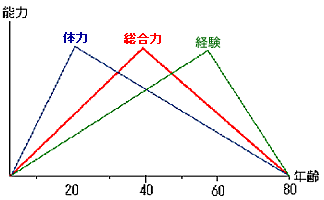 図表 年齢別総合能力比較:0807年齢と能力
図表 年齢別総合能力比較:0807年齢と能力 |
この間、確かに社会的経験も増したし、それ以上に、社会からもそれなり「扱い」を受けるようになった(註:一般社会では「50歳は、立派な大人」で、会社なら部長とか取締役になれる。ただし、私が身を置く宗教界は、「50、60歳はまだまだ子ども扱い。70歳になってやっと一人前。80、90代でますます元気」というとんでもない世界である)。しかし、十年前には想像もしなかった老眼が進行し、初対面の人から渡された名刺の電話番号やメルアド等の判読は不可能になった。おかげさまで、今のところ歯の状態は完璧であるが、その完璧を維持するために1回10分以上かけて歯を磨いているし、年に3回程度定期的に歯医者を受診してケアしている。中性脂肪や肝機能を調べる血液検査は年4回だ。しかし、最も「衰えた」と感じるのは、やはり「脳力」である。以前は、暗記している拝詞(神式のお経)を口で唱えながら、まったく関係のない内容の原稿を書くことができたし、誰かと面と向かって喋りながら同時に、隣で喋っている第三者の会話の内容を理解してその問題点を指摘するという離れ業も難なくできた。ところが、最近は、隣の人の話どころか、面と向かって喋っている人の話も、ちょっとセンテンスが長くなると、はじめのほうで何を言っていたのか解らなくなって、「もういっぺん言うて」と平気で問い直すことも珍しくない。
140億個あるといわれるヒトの脳細胞は、一般の体細胞のように日々再生されずに、普通の状態でも1日に10万個ずつ死ぬ(壊れる)そうだから、十年経てば3億数千万個の脳細胞が死んだことになる。脳細胞の壊れる場所が「どうでも良い」部分なら、そのダメージはたいしたことはないが、運悪く、重要な臓器の機能をコントロールしている部分が壊れたら、それこそ「お終い」である。これは完全に“運”である。たとえ、全脳的にまったく平均的に壊れていったとしても、これはかなり大きい数字である。最近は、喋っている途中ですら、自分の喋っている内容を忘れることもままあるので、おそらく脳内で細い血管が何本か「詰まって(梗塞して)いる」ような気がする。この十年の間に、祖父と父を見送ったが、ご両人の最晩年の脳のCT画像などを見ると、結構、萎縮していくことを知った。そこで、私は、50歳を期して、最新のMRI・MRA・CTからPETまで脳ドックのフルコースを受診することにした。私は、PETの開発に深く関わった大脳生理学研究の先生に、学生時代から可愛がっていただいていたから、その草創期からこの手の医療検査機器について、原理的にはよく知っていたが、おかげさまで、この歳まで重篤な病気に罹ったことがないので、実際にお世話になったことはこれまで一度もなかった。
▼国連に加盟して50年
さて、ひとくちに「50歳」と言っても、かつては「人生五十年」などと言われたが、先進国である日本では、「人生八十年」と呼ばれるようになって久しいので、50歳にかつての時代のそのままの価値があるかどうかと問われれば、そう簡単には答えることはできない。なんでも、この国には「百歳以上」の超高齢者が三万数千人もいるそうだから、その境地から見れば、まだ「折り返し地点」ですらない。織田信長が愛唱していたことになっている(『平家物語』から題材を取った)幸若舞『敦盛』の「…人間五十年、 化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり。一度生を享け、滅せぬもののあるべきか。これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ…」はあまりにも有名である。ただし、歴史上の信長は、満48歳で没したので、正確に言うと五十年の人生を経験していない。歴史上の人物では、松尾芭蕉(1644〜1694)や西郷隆盛(1827〜1877)が満50歳で没した訳であるが、芭蕉なんかもっと「枯れた老人」のイメージがあるであろう。元禄時代の50歳は「老人」だったのである。また、満40歳の時(1867年)の西郷は、まさに倒幕維新を成し遂げた絶頂期で、その時点では、十年後にまさか自分が「賊軍」となって、長年苦労を共にした大久保率いる明治政府軍に討たれるなどとは考えもしていなかったであろう。まさに、「一度生を享け、滅せぬもののあるべきか」である。
歴史上の個別の人間と比べてもキリがないので、「三宅善信」という人間の「時代性」ということを考える上で、今年「満50年」を迎えたものをいくつか採り上げてみたい。たまたま1958年(昭和33年)に起こった出来事という以外に、一見、お互いになんら関係がないと思われる以下の数項目を日付別に採り上げて、その後の50年間の変遷を見て、日本社会の変化について考察してみたい。
1月1日、日本は初めて国連安保理の非常任理事国に選出された。第二次世界大戦の敗戦国であった日本が、戦勝国の枠組みで構成された国連安保理のメンバーに選出されるという画期的な出来事である。そもそも、「United
Nations」は、日本では「国際連合」と訳しているが、これは日独伊三国同盟を中心とした「枢軸国(Axis Powers)」(註:日独伊以外に、ブルガリア・ハンガリー・タイ・ルーマニア・フィンランド等)に対抗する米英仏支(中華民国)ソの「連合国(United
Nations)」となんら変わらず、日本の敗戦直後の1945年10月に、51カ国によってサンフランシスコで結成された。したがって、日独両国には現在でも「旧敵国条項」が適用されているし、米英仏中(中華人民共和国)露の5カ国は現在でも「拒否権」を持つ「常任理事国」として特別の地位を与えられている。その「無条件降伏」から11年経過した1956年12月に、日本は80番目の加盟国としてやっと国連加盟を承認された。その日本は、加盟から1年あまりで安保理の非常任理事国(註:全加盟国の中から、常任理事国を除く10カ国が任期2年間で選出される。選出には、総会で3分の2以上の賛成が必要)に選出されたのは、既に日本の国際的地位が極めて高かったことの照査である。
その後、日本は現在まで9回(18年)にわたって非常任理事国に選出(註:来年1月1日からの任期の非常任理事国にも立候補している)されており、現在の加盟国数(192カ国)で計算すれば、ある国が非常任理事国に選出される確立は、10÷(192-5)=0.053…であるから、100年間の内で約5年間ということになるので、52年間で18年間(100年間に換算すれば28年間)非常任理事国を務めたことは、南米の雄ブラジルと並んで最多である。しかし、52年間を通して、日本は国連の分担金を平均約20%負担してきたのだから、その財的「貢献」と比較して、評価が極めて低かったともいうことができる。2005年の国連創設60周年の際の国連の組織改編機運が盛り上がったときに、日本政府も「常任理事国入り」を目指していろいろ取り組んだが、その試みが悉く失敗に終わったことは、記憶に新しい。本件については、拙文『なぜ日本は常任理事国になれないのか』をお読みいただきたい。この時のトラウマが、インド洋での自衛隊による給油活動や、アメリカを盟主とする対イラク戦争有志連合への自衛隊の派遣という形で現れていることは言うまでもない。だから、こと国際政治に関しては、この50年間、ほとんど日本の地位は上昇することがなかったと言って良いであろう。
▼日劇、月光仮面、売春防止法
他にも、この年にはいろいろなことがあった。2月8日には、有楽町の「日本劇場」(現在、有楽町マリオンが建っている場所)を会場にして、『ウエスタン・カーニバル』が開催された。芸能プロダクションの雄「渡辺プロダクション」を夫の渡辺晋と一緒に設立した渡辺美佐が、興行の端境期に当たる2月のスケジュールを埋めるために思いついたギャラの安い若手ミュージシャンに「ウエスタン」をやらせたのが大当たりして、ロカビリーが爆発的人気を博した。当初は「ロカビリー三人男」と呼ばれたミッキー・カーチス、平尾昌晃、山下敬二郎らが活躍したが、1960年代後半になると、「ジュリー(沢田研士)」と「ショーケン(萩原健一)」が人気を二分したザ・タイガースとザ・テンプターズ。さらには、堺正章と井上順がツインヴォーカルを務めたザ・スパイダース(もちろん、サイドギターのかまやつひろしやリードギターの井上堯之も忘れてはならない)をはじめとする「グループサウンズ(GS)」が一世を風靡した。この『日劇ウエスタン・カーニバル』は、1981年に日本劇場が解体されるまで毎年開催されたが、20世紀後半の日本の音楽シーンに与えた影響は計り知れない。
2月24日、川内康範(註:川内氏については、2007年11月15日に発表した拙エッセイ『インドの山奥で…』を参照されたい。因みに、川内康範氏は本年4月6日に享年88で逝去)原作の日本テレビ界初のスーパーヒーロー連続冒険活劇『月光仮面』がTBS(当時はJOKR)から放送開始された。本放送は、1年半という期間に過ぎなかったが、この何ら超能力を持たない等身大の「正義の味方」が、当時の日本社会にいかに認知されていたかは、平均視聴率40%(最高視聴率は67%!)という、とんでもない高視聴率をたたき出したことからも明かである。もちろん、『けっこう仮面』(永井豪)や『鶴光仮面』(笑福亭鶴光)といったように、まったく異なった分野にパロディ作品を派生させたことも、「月光仮面」というヒーローがいかに、いわずもがなの“常識”として捉えられていたかの証明である。
ただ、当時、月光仮面の真似をして高所から飛び降りてケガをする少年が続出した(言うまでもなく、飛び降りる少年がバカ)ことにより、新聞や週刊誌から「有害番組」と指弾されて、惜しまれつつ放送が打ち切られた。もし、『月光仮面』が「有害番組」だというのなら、細木数子や江原啓之をはじめとする「霊視」や「運命鑑定」といった明かな『放送法』や民放連による『放送倫理基準』に違反している有害番組を垂れ流し続けている現在の民放各社こそ糾弾されるべきである。「正義の味方」月光仮面が疾風のように現れて、これらの有害番組のプロデューサーを成敗してくれることを願っているのは、私だけではあるまい。つまり、「放送倫理」という点では、何もかもが手探り状態であったこの放送草創期の頃(註:この年の5月16日に、わが国のテレビの契約総数が100万台を突破)のほうが、はるかにまともなのは何故だろう?
4月1日には、『売春防止法』が施行された。いわゆる「赤線廃止」というやつである。私は、当時、法務大臣秘書官を務め、「赤線廃止」の実務に当たり、後に、某私立大学の理事長まで務めた人物(本業は、神職)から、本件については直接、薫陶を受けたが、一言で言って、数千年前に“貨幣”という「あらゆる物(サービス)と物(サービス)を交換可能にする装置」が人類社会に出現して以来、連綿と続いてきた“売春”という行為がなくなるとはとても思えない。女性側の同意を得ない「レイプ(rape)」の歴史は、人類の歴史と同じ長さがあるであろう。否、もっと長い歴史があるであろう。おそらく「類人猿(ape)」の時代からあったであろう。わが国においても、「遊女」の歴史は古い。
時の権力が当該行為を公認するという「公娼制度」についても、源頼朝が新田氏一門の里見義成(註:数百年後『南総里見八犬伝』の舞台となる安房国の大名家の祖)に「遊女別当」という官職を設けたことが記録に残っている。もちろん、その前の時代に、平清盛の愛妾の祇王や源義経の愛妾静御前らの白拍子もそういった面を持っていたことは明白である。わが国においては、吉原をはじめとする江戸時代の遊郭においても、遊女は高い「教養」や「芸」を要求される知的な職業でもあった。明治維新直後の1872年に、英国が清国で行っている奴隷売買を批判した明治政府が、逆に欧米列強から「遊郭(年季奉公)こそ人身売買だ」と批判されたので、『芸娼妓解放令』を太政官布告という形で発布した。しかし、その実効性が乏しかったことは、日露戦争直前の1900年に、『娼妓取締規則』が施行された(つまり、「取り締まる」対象が厳然とあったということ)ことからも読み取れる。
同様のことは、敗戦後の1947年、GHQの指令に基づく『婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令』が発せられ、「公娼制度」は名目上、廃止されたが、新宿二丁目などの「赤線地帯」が温存されたため、実行のあるものではなかったことは言うまでもない。しかも、この『売春防止法』の施行によって、法律上は「存在しない」ことになった「売春」行為は、それ故、余計に巧妙化して、日本全国へとばらまかれてしまった。そして、21世紀の現在、インターネットや携帯といった情報通信ツールを用いた「出会い系」をはじめとするさまざまな「性の商品化」が以前にも増して蔓延していることは、今さら論述するまでもない。
▼どうなった日本の労働組合
先を急ごう。4月5日には、「巨人軍の長嶋茂雄、四連続三振で公式戦デビュー」という項目があるが、私は個人的に長嶋茂雄が嫌いなので、本件についてはこれ以上記さない。後でメジャーになると、若い頃の失敗も「大物の片鱗」と見なされるのがこの国の風習か…。ただし、この試合の対戦相手は当時、日本プロ野球界のエース金田正一(ハングル読みなら「キム・ジョンイル」)が所属した球団「国鉄スワローズ」を所有していた日本国有鉄道公社(国鉄)は、労使共に「親方日の丸」体質でその後も赤字垂れ流し続けた結果、1987年に廃止され、JR各社に分割民営化されたことは言うまでもない。因みに、現在の読売ジャイアンツの原辰徳監督は、この年の7月22日にこの世に生を受けた。
また、「親米保守」の岸信介内閣の治下、この年は、やたらと労働争議が勃発した年でもあった。春闘では私鉄の24時間ストをはじめとする全産業を挙げてのゼネスト状態であったとも言える。3月21日に始まった炭労ストは6月18日まで3カ月間に及んだ。9月15日から始まった総評・日教組による勤務評価反対全国統一行動は11月26日まで続いた。しかし、50年後の今日、相変わらず自民党政権は「アメリカの手下」であることは変わらないが、炭労は炭坑(石炭採掘産業)そのものが日本から消滅し、総評は、1987年に設立した連合に合流するため1989年に解散された。
それから、「右寄り」の人々から何かと悪口を言われる日教組であるが、私は、日教組にははじめからそんな力はないと思っている。子どもたちの“学力”が低下したしたのも、陰惨な“いじめ”が起こるのも、日本の社会情勢の変化であって、テレビの有害番組と比べたら、日教組なんか、子どもたちに「悪しき影響」を与えるほどの中身も実力もない。さもなくば、日教組の組織率(註:全小中高の教職員に占める日本教職員組合員の占める割合)が1958年には86%もあったのに、2008年では28%という体たらくであるが、組織率の極端に低くなった現在のほうが、はるかに子どもたちの「レベルが下がっている」という事実をどう解釈するのだ。もし、「日教組が諸悪の根元だ」というのなら、日教組が弱体化した今の子どものほうが「よい子」になっているはずだが、結果は逆である。「取るに足らない団体」として、無視しても差し支えない。
過去五十年間、日本の労働組合は、正規雇用者である自分たちの既得権の保護だけに汲々としてきた感がある。しかも、労働組合員の多くは、「親方日の丸」の公務員であったり、一部上場の大企業のサラリーマンであったりして、当初から、組合さえ結成することができないような町工場や家族的経営の商店といった、定休昇級やボーナスはおろか、有給休暇も失業保険も福利厚生とも無縁な“労働弱者”のことなんかに目もくれずに、イデオロギーに走ったり、「お殿様スト」や「お姫様スト」に明け暮れていたのである。その間、日本の高度経済成長によって、外国人労働者や非正規雇用といった割合がドンドンと増加して行き、また、経済のグローバル化に伴って、大企業は人件費の割安な海外へとその生産拠点を移していったので、日本の労働市場は空洞化の一途を辿ったのである。
▼日本の出産環境について
5月24日には、完成したばかりの国立競技場で、「アジア版のオリンピック」とも呼ばれる「第3回アジア競技大会(Asian
Games)」が開催された。さすがに、「アジア版のオリンピック」と呼ばれるだけあって、カバディやセパタクローや空手などのIOCが主催するオリンピックにはないアジア独特の競技種目がある。他にも、ボウリングやビリヤードといった競技種目とは思えないスポーツもある。このアジア競技大会は、11月1日に、東京・神戸間を7時間で結んだ特急「つばめ」が開業した。戦前から一貫して、「燕」は国鉄を代表する特急であって、最後部に展望デッキを持つ列車であったが、この1958年に営業を始めた「つばめ」は、6年後の1964年に開通する東海道新幹線「夢の超特急」ひかりと「東京オリンピック」とセットになっていると考えて良い。共に、日本の「戦後」の終了と「行動経済成長」社会への移行を象徴する出来事であった。
7月27日には、三宅善信が誕生した。私は、三人兄弟の次男だが、2歳年長の兄と私は助産婦(産婆)の助けによって自宅の産室で産まれたが、出産時に母の体調が思わしくなかったので2歳年少の弟は病院で産まれた。かつては、ほとんどの出産が自宅で行われたが、現在では、ほとんどの出産は、正常分娩・異常分娩の如何にかかわらず、病院で行われる。しかしながら、本来、年中無休24時間いつ産気づくか判らない出産という生理現象を、営業時間帯の限られている病院で行うこと自体の問題と、産科医の極端な不足は、周産期医療の抱える様々な問題に提起している。多くの地方都市の産婦人科病院では、正月休みやゴールデンウイークやお盆休みの前には、連休中の医療スタッフが手薄な時期に出産が行われては対処しきれないので、その前週に陣痛促進剤を投与して、強制的に出産させているのが一般的である。この事実は、市役所の出生届出数を確認すれば一目瞭然である。本来なら、日本全国で生まれてくる新生児の数を合計すれば、1年365日、毎日生まれてくる新生児の数はほぼ同じ数のはずであるが、ここ十数年は、上記の期間の1週間前の出生数は、ほぼ通常の2倍の赤ちゃんがこの世に生を受けていることになる。
現在、医科大学で産婦人科を専攻する学生は、年間400名程いるが、その内約300名は「不妊治療」等の分野に進むので、実際に「産科」医となるのは、全国で年に100名程度で、各県当たりでは2名しかいない計算になる。産科医の診療報酬の点数を3倍くらいに引き揚げて、もし、出産時の医療事故が起こって訴訟になっても、医師個人への「刑事責任は問わない」ということと「損害賠償はすべて医療機関が保険に加入して支払う」ということを制度化しなければ、いくら医師の総枠数(医学部の入学定員)増をしたとしても、実効がないことは目に見えている。「少子化」対策を論じる前に、出産環境整備を行うべきである。
ここで述べたように、日本では「病院で出産する」ことが常識になっているが、私の知人のオランダ人女性(子ども3人)に尋ねると、オランダでは近所の助産婦の助けを借りて出産するのが常識だそうが、「日本では子どもは病院で産まれる」と言ったら、驚いていた。この辺り、これからの少子高齢化社会を考える上で参考になると思う。日本では、2002年に「看護婦」や「保健婦」を「看護師」や「保健師」と呼称変更した際に、調子に乗って「助産婦」も「助産師」と変更したそうであるが、その一方で、この職業は、現在でも、女性しか就くことができず、日本では、役人が構造的な問題に対峙することなく、いかにつまらないことに拘っているかの査証でもある。
因みに、7月27日に生まれた有名人とその生まれ年を記しておくが、ここに登場する人物を比較するだけでも、いかに誕生日占いが、姓名判断や血液型占いなどとともにバカバカしいものであるのか判る。スハルト(インドネシア大統領、1921年)、大山倍達(空手家、1927年)、塩田丸男(政治評論家、1924年)、高島忠夫(俳優、1930年)、有吉道雄(プロ棋士、1935年)、ひろさちや(仏教評論家、1936年)、三浦和義(実業家?、1947年)、かわぐちかいじ(漫画家、1948年)、渡嘉敷勝男(プロボクサー、1960年)、アレックス・ロドリゲス(大リーガー、1975年)。皆さん、7月27日生まれであるが、なんの共通性もない。
▼ベトナム戦争とチキンラーメン
「誕生」繋がりで言えば、この年の8月25日、その後、世界を席巻することになる画期的な食品が大阪梅田の阪急百貨店で売り出された。日清食品の「チキンラーメン」である。台湾出身の安藤百福が、戦後の食糧難期にアメリカから食糧支援された小麦粉がほとんどパンに加工されているのを見て、なんとか東洋人に馴染みのある食材の麺類にできないものか?
と考え、開発されたと言われる。今でこそ「ラーメン」という呼称が普及しているが、インスタント食品でなくとも、屋台で販売されているラーメンも、チキンラーメンが販売されるまでは、一般的には「支那そば」とか「中華そば」と呼ばれていた。チキンラーメン開発にまつわる安藤百福の苦労談やエピソードは、良く知られているので、割愛する。
 現在販売されているチキンラーメンのパッケージには
現在販売されているチキンラーメンのパッケージには
「50周年」のマークが印刷されている |
ただ、このインスタントラーメンという食品は、ベトナム戦争があったからアメリカ社会に普及したということは案外知られていない。1966年にアメリカに進出したが、今では、米国中のスーパーマーケットでコーナー販売されている「チキンラーメン(Oodles
of Noodles)」も、そもそも、ラーメンを食するための必需品である「丼」と「箸」という食器のなかったアメリカでは、最初の数年間はあまり売れなかった。ところが、その便利性から米軍の調達品となり、ベトナム戦争に従軍した米兵にとってジャングルでの貴重な食糧となったのである。アメリカ式の正規の食べ方は、マグカップに入れて熱湯を注いで(註:アメリカでは、インスタントラーメンは「noodle
soup」と呼ばれる「具だくさんスープ」として認識されている)フォークで食するが、夜間のジャングルで火を熾(おこ)すと、敵軍から銃撃されるので、生火を用いることができないときには、チキンラーメンに湯を注がずに、そのまま「スナック」として食した。他のインスタントラーメンのように、粉末スープやレトルトスープを後で加えるというような洗練された製法ではなく、味付き麺にただ熱湯を注ぐというだけのシンプルな調理法のため、逆にそのまま齧るという食べ方もできる。基本的に、アメリカ人は日本人より「濃い味付け」を好むことも有利に作用した。
ベトナム滞在中(飢えた人間は、なんでも美味しく感じられる)にチキンラーメンの濃い味に病みつきになり、帰還後にも、日常的にこれを食するようになったのである。現在の国別のインスタントラーメンの消費量は、1位中国・2位インドネシア・3位日本・4位アメリカ・5位ベトナムと続く。食習慣のよく似ている欧米人と同士でも、19位の英国、23位のドイツの約20倍、29位のフランス至っては約100倍もアメリカ人はインスタントラーメンを食しているのだから、アメリカ人のインスタントラーメン好きは“異常”と言っても良いであろう。その影に、ベトナム戦争という歴史が隠されていることを指摘しておかなければなるまい。
因みに、1971年には「カップヌードル」が発売されたが、これは丼や箸という食器のないアメリカ人の、四角い乾麺を二つに割ってマグカップに入れて熱湯を注ぎ、フォークで食するという食べ方から逆に考案された食品で、もちろん、ベトナム帰還兵のたくさんいたアメリカにおいても市民権を得たが、日本でも野外で食事を摂ることの多い自衛隊や機動隊の調達品となり、1972年の2月に起きた「あさま山荘事件」が国民の耳目を一身に集め、一日中実況中継が行われ、NHKと民放の視聴率を合わせると、なんと90%近い日本人がその画面を食い入るように見つめたが、その中で、氷点下15℃という極寒の地で、機動隊員たちが暖かい湯気の立ち上るカップヌードルを美味しそうに頬張るシーンがテレビに映し出され、このインスタント食品は華々しいデビューを飾った。チキンラーメンといい、カップヌードルといい、凄惨な戦いの現場が「完全調理済み食品」を求め、それがファッション化するという極めて20世紀的な食品だと言えよう。
▼50年間で激減した台風の人的被害
9月27日、狩野川台風(昭和33年台風22号)が神奈川県に上陸し、関羽地方を中心に、死者・行方不明者1,269名、全半壊流出家屋約16,000戸という甚大な被害をもたらせた。この台風は、9月21日にグアム島の東海上で発生したが、その後、勢力を成長させ、24日にはアメリカ軍の観測で中心気圧877hPa(当時の単位はミリバール)という、当時観測史上最強のスーパータイフーンとなった。日本列島へ上陸時には960hPaと急速に弱まったが、秋雨前線を刺激して東日本に大雨を降らせた。私がここで問題にしているのは、当時の日本では、まだ死者が千名を超す台風祭が珍しくなかったということである。もちろん、現在でも、台風が日本列島を直撃すると、死者・行方不明者が発生するが、それでも、その数はせいぜい数名からいくら多くとも、二・三十名程度である。
もし、百名以上の死者・行方不明者が出たら、気象庁による予報のあり方や行政当局の避難誘導が適切であったかどうかが問題となって、おそらくかなり厳しい政府への責任追及となるであろう。台風は、その発生から日本列島への接近まで通常、数日間の余裕があるので、その間に適切な対応が取れたはずであるからである。その点、「予測不可能」ということになっている地震においては、たとえ6,440名の膨大な死者・行方不明者を出した阪神淡路大震災(1995年)においても、気象庁も政府もほとんど非難されていないこととは対照的である。
実は、1950年代までは、死者・行方不明者数が千名を超える台風が度々、日本列島を襲っている。というか、その後も、毎年のように台風が日本列島を直撃しているが、河川の護岸や太平洋側の大都市部の防潮堤の整備等によって、台風の人的被害は1960年以後には激減しているのである。敗戦から1カ月しか経っていない1945年の枕崎台風は、3,756名の犠牲者を出したが、この時は天気予報など機能しなくて、廣島だけで千名以上の死者が出た。しかし、この台風による大雨で広島市街を汚染していた放射能が一掃されて、その後、思いの外早く広島に人々が住めるようになったという節もあるそうだ。他にも、九州を縦断しいったん日本海に出てから北海道を襲った1954年の洞爺丸台風では、1,761名の犠牲者と20万戸の全半壊。東海地方に甚大な被害をもたらせた1959年の伊勢湾台風では、5,098名の犠牲者と全半壊流出した家屋が16万戸にも達した。
因みに、江戸時代にはもちろん天気予報なんぞはなかったので、備えもなくいきなり日本列島に台風が1つ上陸する(註:年平均2つの台風が日本列島に上陸する)と、基本的には土で造られた堤防があちこちで決壊し約5,000名の犠牲者が出たというのも、あながち無理な数字ではないであろう。そして、それが稲刈り前であれば、約100万石の減収となった。すなわち、台風が1年に2つ上陸するとしたら、年平均200万石の減収となり、日本全国の米の総生産量である2,000万石の10%にも及んだ。現在では、稲の作況指数が90%になったら、大変な凶作である。当然、その地方は飢饉に見舞われた。一方、近畿地方を中心に、約61,000戸の全半壊家屋をもたらせた1961年の第二室戸台風(註:大阪市内のかなり多くの場所が浸水した。高潮で辺り一面が水浸しになったわが家では、池にいた鯉があちこちを泳ぎ回り、高潮が引いた後、池から何十メートルも離れた庭でのたうち回っていた光景を私は明確に記憶している)の犠牲者が202名に過ぎなかったということからも判るように、1960年代以後、「土建国家」日本の社会インフラが急激に整備されていったことが容易に理解できるであろう。
▼ミッチーブームと皇室の将来
11月27日、宮内庁から皇室会議(註:皇室の重要事項について決定する機関。皇族と三権の代表ら10名によって構成される機関。内閣総理大臣が議長を務める)が、「日清製粉社長正田英三郎の長女美智子を皇太子妃に迎えることを可決した」と発表した。将来「皇后」となる皇太子妃が、皇族や五摂家等の特別の家柄からではなく“平民”(註:もちろん、日本国憲法に「平民」という概念はなく、「皇族」以外はすべて「国民」である)から選ばれたことは、13年前の敗戦によって根本的に変化した天皇と国民との関係を、非常に解りやすい形で示す「新しい契約」の意味が込められた。しかし、そのような深い政治的宗教的意味とは関係なく、メディアと国民はこの慶事を「テニスコートの恋」と囃し立てて、20世紀の「シンデレラストーリー」いわゆる「ミッチーブーム」に湧いた。因みに、この年、『週刊大衆』、『週刊女性自身』、『週刊明星』、『週刊実話』などの創刊が相次いだ。当然、これらの新しいメディアである週刊誌は、従来は「賢き辺り」と呼び変えて直接的な表現をすることさえ憚られた皇室に関する報道合戦を繰り広げ、また、国民も挙ってそれらを買い求め、現在に至るまでの「週刊誌報道」の原型を確立した。
この「ミッチーブーム」は、翌年4月10日の「世紀のご成婚」で頂点に達した。ご成婚パレードを一目見ようと53万人が沿道に詰めかけ、その様子をNHKが実況生中継するということで、1年前には100万台であったテレビの登録台数も200万台を突破した。このミッチーブームは、さらに翌々年2月23日の皇太孫「浩宮」徳仁親王の誕生後も続き、戦後の皇室報道のあり方を決定づけた。しかし、皇族に関する報道は、憲法に定められた天皇の国事行為や行幸啓(国体や植樹祭等の恒例行事や大規模災害の被災地への見舞い等)といった「公的なもの」だけでなく、幼い三人の宮様たちの運動会や学芸会等といった「私的なもの」まで採り上げられるようになり、その後の皇族の人たちの価値観にまで多くの悪影響――つまり、国民に「見られている」ということを意識した過剰なパフォーマンスや、その逆である「特別な神聖家族ではない」という意識――を与えたことは否めない事実である。
そのツケは、現在の皇太子ご一家の有り様を見ていれば、誰しも気になるところである。“平民”とはいっても、自ら働いたことのない「深窓の令嬢」であった正田美智子嬢(現皇后陛下)とは異なり、海外生活の長かったキャリアウーマンの小和田雅子嬢(私は、当時、外務省条約局長であった小和田恆氏がハーバード大学の客員教授をしてケンブリッジ市に居住し、雅子嬢も同大学で学んでいた同じ時期にハーバード大学で学究生活を送っていた)を皇太子妃に迎えたことが悠久の歴史を有するわが国の国体護持にとって良かったと思っている人は多くないと思う。第一、今上陛下は、皇太子時代「あの人と結婚したい」などとは仰っておられない。あくまで、皇室会議がいろんな情勢を勘案して正田美智子嬢を皇太子妃に決めたのである。ところが、現皇太子の徳仁親王殿下は、自らの意志で「あの人と結婚したい」と主張し、そのわがままに押される形で、皇室会議が追認したのである。
皇太子妃殿下(雅子様)の振る舞いも気にかかる。誰にも体調の善し悪しがあることは解るが、海外からの国賓の歓迎や、皇族が臨席することが恒例になっている地方での“公務”を「体調が優れない」と言って欠席しながら、愛子内親王の運動会には笑顔で出席しているのである。しかも、そのことに対して、皇太子殿下が「反省」されている様子も見受けられない。場合によっては、「海外での療養生活も…」などという意見が上がることさえ、嘆かわしい限りである。悠久の歴史を有するわが皇室において、そう遠くない将来に皇統を継承される立場にある人が「個人的な望み」なんぞ言ってよいはずがない。まさに、天命を知るべしである。人それぞれ、自分の好むと好まざるとに関わらず、この世に生を受け、しかも、どの時代のどの国のどの家でどの性別で生まれるかすら、自分で決めることができないのであるから、逆を言えば、その人が生まれた時代や国や家や性別といった条件は、アプリオリなものとして、受け入れるべきであると私は考えている。読者の諸氏はどのようにお考えであろうか?
▼聖徳太子を描いた最高額紙幣は金融危機鎮静化の守り札
だいぶん長々と書き連ねてきたが、もう少し辛抱してお付き合い願いたい。齢を取ると、文章が冗長になるものと大目に見ていただきたい。12月11日に、最高紙幣として一万円札が発行された。言わずと知れた「聖徳太子」の絵柄が描かれた「有り難〜い」一万円札である。意外なことに、聖徳太子がわが国の「紙幣の顔」として登場したのは、昭和に入ってからである。近代国民国家の主権統治行為のひとつとして、「紙幣の発行」があるが、明治・大正期には、「皇国史観」に基づいて国体護持に功績のあった「功臣」という観点から、武内宿禰(たけしのうちのすくね=大和朝廷初期の景行天皇から仁徳天皇までの二百数十年間にわたって仕えたという伝説的功臣)や藤原鎌足や和気清麻呂や菅原道真といった人物が主に紙幣を飾った。当時としては最高額紙幣であった百円札に登場したのは私の父が生まれた1928年(昭和3)12月のことである。
この前年(1927年)の5月に、まだ資本主義の発展段階にあった日本を金融恐慌が襲ったのである。直接のきっかけは、その4年前に帝都を灰燼に帰せしめた関東大震災の復興債の返済繰り延べ(デフォルト)を巡る大蔵大臣の不用意な国会答弁がきっかけとなって、銀行の取り付け騒ぎが起こった。その2年後には、世界の金融経済の中心地、ニューヨークのウオール街が株価の大暴落が起こり、金融の国際協調体制などなかった当時としては、各国政府は、不況に対する国民の目を逸らし、「経済刺激策としての戦争」というオプションを取らざるをえなかったという一面もある。このような未曾有の経済金融の中で登場したのが、聖徳太子の百円札(兌換券)であった。以後、敗戦後のインフレに対処するために1950年に発行された千円札、同じく、高度経済成長の魁となった1957年10月に発行された五千円札、そして、翌1958年12月に発行された一万円札と、相次いで高額紙幣(日本銀行券)が発行されたが、いずれも、その券面を飾ったのは「和を以て尊しと為す」の聖徳太子であった。
しかし、よくよく考えてみると、それ以来、50年間の長きにわたって、わが国の最高額紙幣は一万円札のままである。このことは、インフレが常の近代国家にとっては、異例中の異例と言って良い。しかも、その間、ほぼ右肩上がりで経済成長してきたのであるから、いかに日本が「インフレなき経済成長」をなさしめたかが判ろうというものである。1958年当時の大卒の初任給が15,000円程度であったので、新しく発行された一万円札1枚と五千円札1枚の2枚あれば、給料袋が満たされたことから想像しても、いかに有り難〜いお札であったかご理解いただけるであろう。因みに、その当時から現在まで、初任給は約15倍に伸びたが、消費者物価指数は約5倍しか伸びていないので、現在のほうが3倍は豊か(暮らしが楽)になったと言える。ただし、ここ10年ほどはサラリーマンの実質年収は減少し続けているので、21世紀の日本は、かつてのような「頑張って働きさえすれば、来年は去年より必ず豊かになる」というような夢が抱けなくなっていると言えよう。昨年から問題になってきた米国のサブプライム問題に端を発する経済破綻は、近い将来、必ずや世界的な金融恐慌に発展するであろう。われわれは、一万円札誕生50周年の今年、経済についても、もっと歴史から学ばなければならない。
▼テレビというメディアの果たしてきたものと将来
さて、昭和33年の出来事も、残すところあとひとつとなった。それは、12月23日に、東京タワーが完成した(註:工事期間は、1957年6月29日から1958年10月14日までの16カ月間)ということである。パリのエッフェル塔よりわずかに8m高い「世界一」の高さを有するテレビ塔ができたことに意味は大きい。敗戦国であった日本が、立派に復興し、再度、世界の一等国を目指していこうとする誰の目にも一目で判るシンボルであった。それは、この塔の正式の名称が「日本電波塔」であることからも意気込みが伝わってくる。ただし、この塔を正式名称である「日本電波塔」と呼ぶ人は、完成当初から誰もいない。皆「東京タワー」と呼んだ。
 篤姫縁の増上寺を訪れ、
「同い年」の
篤姫縁の増上寺を訪れ、
「同い年」の
東京タワーをバックに記念撮影する筆者 |
また、一番でかい物を破壊することによって、自らの圧倒的なパワーを見せつけるシンボルとして、ゴジラやモスラやガメラといった怪獣たちは、戦後日本の復興のシンボルである東京タワーに挑みかかったのであろう。私は子どもの頃、何度怪獣に破壊されても、また次の映画が撮影されるまでには、立派に復興している東京タワーという現代のバベルの塔が不思議でならなかった。そして、そのようなシンボル的存在を見て育ったアニメ世代の人々が、昭和33年の東京の下町を舞台に制作した2005年公開の映画『ALWAYS
三丁目の夕日』でも、また、2004年にリメイク版としてテレビ東京から放送された『鉄人28号』においても、建設中の東京タワーが、時代背景として印象的に描かれている。
先ほどの「ミッチーブーム」の項目で述べたように、1958年の一年間だけで、テレビの契約台数は100万台から200万台へと2倍に伸びた。ある意味、この半世紀の間において、日本人に最も大きな影響を与えたものは、政治でもなければ、宗教でもなければ、活字メディアでもなかった。それは間違いなくテレビであろう。テレビの影響力の前にあらゆる権威は屈服した。ノーベル平和賞まで取った内閣総理大臣としては、7年8カ月という最も長い在任期間を有する佐藤栄作氏も、その退任記者会見(1972年6月)の際には、それまで「権威がある」と信じられてきた新聞記者を追い出して、テレビカメラに向かって直接国民に訴えかけたエピソードは今でもハッキリと記憶に残っている。そして、善きに付け悪しきにつけ、ごく一部の人々の恣意的な意図によって作成されるテレビが日本の社会を動かしてきたと言える。
このテレビという巨大なメディアに対して、新たに到来したインターネットがどれだけ、社会を変えてゆくことができるかは、まだ道半ばである。しかし、この50年間誰も揺るがすことのできなかったテレビの座をインターネットが揺るがしたことだけは、確かな事実である。双方向性を有するインターネットの登場に危機を感じたテレビ界は、地上波デジタル化(地デジ)へと突っ走った。50年前に竣工した東京タワーは、当然のことながら、デジタル放送などというものを想定して立てられたのではないことから、「第二東京タワー」の建設の必要性を説く者が出てきた。総務省の方針では、2011年7月24日に従来のアナログ放送は終了し、日本国内のテレビ放送は、地デジでなければ、衛星放送かケーブルテレビかワンセグかということに限定されることになった。そこで、新世紀の東京タワーとして、墨田区に高さ610mの「東京スカイツリー」の建設が決定され、本年7月14日に着工されたのである。さて、このタワーが新たな時代のシンボリズムとして、日本国民に受け入れられるか否かは、新たに作られるゴジラ映画で破壊されるかどうかに懸かっていると考えるのは私一人だけであろうか。
このように、半世紀前の1958年に視点を当て、世の中の変遷を見ていくことによって、今後、起こってくるであろうことの予見を試みたが、はてさて、満50歳を迎えた私の「天命」はいったいどこにあるのだろうか?
誰も明日何が起こるかは判らないが、ただ言えることは、プロイセンの鉄血宰相ビスマルクの言うように、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」ということである。十年後の拙作『六十而耳順』を楽しみに待っていてほしい。