レルネット主幹 三宅善信
▼ 神経伝達攪乱物質は薬か毒か?
大相撲界の“大麻汚染”が問題になっているが、そもそも「大麻(たいま)」とは、いったい何なのか、皆さんは深く考えてみたことがあるであろうか?
「そんなこと考えるまでもない。“麻薬”の一種だろう」と答える人も多いと思われる。でも、こんな単純な答えで満足するようでは、「ものごとの本質を解っていない人」と思われてもいたしかたあるまい。もし「麻薬(drug)」を、「依存性の強い幻覚・酩酊・向精神作用などをもたらす物質」と規定するなら、酒(アルコール)も煙草(ニコチン)も皆「麻薬」ということになってしまう。「発癌性」などという点から言えば、むしろ、酒や煙草のほうが麻薬よりも遥かに危険である。にもかかわらず、「百害あって一利ない」酒や煙草は、多くの国で政府が高い税金を課してまで自国民を「中毒症状」にさせている(奨励している といっても良い)のに、麻薬のほうはほとんどの国では厳しく規制されている。また、それ故、やくざやマフィアの資金源になったり、アフガニスタンやコロンビアのようにテロリストやゲリラの軍資金になっている。
しかし、脳内の神経伝達に作用して「幻覚・酩酊・向精神作用などをもたらす物質」という意味では、ヒト(大脳の発達している多くの哺乳類)の神経伝達作用には欠かすことのできない分泌物(神経ホルモン)であるオピオイド、エンドルフィン、ドーパミン等は皆、ある意味“麻薬”と同じ作用をもたらしている。それ故、「脳内麻薬」と言われたりもする。耐えきれないほどの強い痛みを我慢しなければならない時(例えば、βエンドルフィンはモルヒネの数倍に鎮痛作用がある)や、「報酬系」と呼ばれる欲求が満たされた時、あるいは、満たされることが判った時に快楽を与えるために、自らの脳内で作り出される「ご褒美」である。この脳内で作り出される分泌物とよく似た化学的組成を持つ物質(麻薬)は、外在的に「幻覚・酩酊・向精神作用などをもたらす」が故に、「神経伝達攪乱物質」ということもできる。
これらの化学物質(たとえそれが「生薬」であったとしても、その薬効は生薬に含まれる化学物質が生体に対して起こさせる「化学反応」なのであるから、重要なのは化学物質である)の効果を期待して、医療の現場においても、これらの化学物質は「薬」として盛んに処方される。同じ神経伝達攪乱物質(麻薬)を、医師が「薬」として処方するのはOKで、各個人が「嗜好品」として使うのは不可であるということが、程度の差こそあれ多くの国で法律によって禁止されている。医師の処方による使用が可で、個人の嗜好による使用が不可なのは、精神に変調を来した人――「言葉狩り」が盛んなこの国では、精神分裂病のことを最近「統合失調症」などと言い換えているが、その実態はなんら変わらないことは言うまでもない。
▼ ヒロポンとは「労働を愛する」という意味
因みに、英語では「Schizophrenia(スキゾフェレニア)」と言うが、これはギリシャ語の から来ているが、文字通り翻訳すれば「精神分裂」である――の精神を神経伝達攪乱物質を用いて“正常”に戻そうとする、いわば、「マイナスXマイナス=プラス」みたいな効能を期待(「ダメもと」主義)しているからである。同様の理由で、“正常”な人がこれを使えば、“異常”になってしまう危険性が高い(「プラスXマイナス=マイナス」)という考え方から、そして、多くの麻薬が持つ「依存性」故に、それを得るために何をしでかすか判らない(社会の安寧秩序を乱す可能性が高い)が故に、法律によって、個人による使用のみならず、製造・保有・販売の一部もしくは全てが禁止されている場合が多い。
から来ているが、文字通り翻訳すれば「精神分裂」である――の精神を神経伝達攪乱物質を用いて“正常”に戻そうとする、いわば、「マイナスXマイナス=プラス」みたいな効能を期待(「ダメもと」主義)しているからである。同様の理由で、“正常”な人がこれを使えば、“異常”になってしまう危険性が高い(「プラスXマイナス=マイナス」)という考え方から、そして、多くの麻薬が持つ「依存性」故に、それを得るために何をしでかすか判らない(社会の安寧秩序を乱す可能性が高い)が故に、法律によって、個人による使用のみならず、製造・保有・販売の一部もしくは全てが禁止されている場合が多い。
一般に「麻薬」と言えば、アヘン・モルヒネ・ヘロインなどのケシの実から抽出される物質を元に合成された物質を真っ先に思い浮かべるであろう。これらの化学物質の特徴は、「幻覚」をもたらすと同時に、強い「依存性」も招く。さらに、神経の働きを一時的に活性化させる「覚醒剤」と呼ばれる薬物がある。20世紀のはじめに日本人化学者の手によって漢方薬の麻黄の成分であるエフェドリンが抽出され、鬱血防止や気管支拡張剤として開発された。エフェドリンは、現在でもその交感神経刺激効果を利用して、鼻粘膜の鬱血防止(鼻づまり防止)の薬効から多くの感冒薬(風邪薬)に含まれている。戦時中に、軍隊や24時間体制で兵器を生産した軍需工場で働く人々に広く配布された「ヒロポン」(因みに、このヒロポンも、「労働を愛する」という意味のギリシャ語「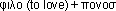
 」に由来)も、エフェドリンから誘導された化学物質のアンフェタミンやメタンフェタミンから製造される「覚醒剤」は、シャブやスピードをはじめ、多くの俗称で流布している。
」に由来)も、エフェドリンから誘導された化学物質のアンフェタミンやメタンフェタミンから製造される「覚醒剤」は、シャブやスピードをはじめ、多くの俗称で流布している。
ここで挙げたの「麻薬」や「覚醒剤」の成分として共通する化学物質は、「アルカロイド(alkaloid)」と呼ばれる。塩基性(アルカリ性)を示すが故にアルカロイドと呼ばれるのであるが、この植物由来の有機化合物は、窒素原子(N)を含んでいる点に特徴がある。光合成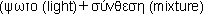 とは、水(H2O)と炭酸ガス(CO2)という単純な構造の物質を太陽光線のエネルギーを用いて、炭水化物(C6H12O6)という高分子にまで合成する(化学エネルギーに変換する)炭酸同化作用であることは言うまでもないが、それだけだと、植物の体内に窒素が吸収されることはない。そこで、葉緑体を持った植物は、豆科植物の根に共生するバクテリアや菌類の助けを借りて、空気中に大量にある(空気の80%は窒素からなる)不活性なガスである窒素をアンモニアや硝酸塩などの窒素化合物の形で吸収している。なぜなら、窒素がないと、身体を構成する蛋白質の材料であるアミノ酸が合成できないからである。それ故、より多くの収穫量が期待される農業には、窒素肥料が欠かせないのである。
とは、水(H2O)と炭酸ガス(CO2)という単純な構造の物質を太陽光線のエネルギーを用いて、炭水化物(C6H12O6)という高分子にまで合成する(化学エネルギーに変換する)炭酸同化作用であることは言うまでもないが、それだけだと、植物の体内に窒素が吸収されることはない。そこで、葉緑体を持った植物は、豆科植物の根に共生するバクテリアや菌類の助けを借りて、空気中に大量にある(空気の80%は窒素からなる)不活性なガスである窒素をアンモニアや硝酸塩などの窒素化合物の形で吸収している。なぜなら、窒素がないと、身体を構成する蛋白質の材料であるアミノ酸が合成できないからである。それ故、より多くの収穫量が期待される農業には、窒素肥料が欠かせないのである。
▼ 大麻は日本人にとっては欠かすことのできない植物
さて、ここで現在、社会的問題にまでなっている大麻(たいま)について考えてみよう。日本では、「大麻取締法」によって麻薬の一種と分類される「大麻」は、アサ植物の一種である大麻草の葉・花・実から採取され、麻薬としては、一般に乾燥大麻(marijuana)や大麻樹脂(hashish)という形で流通している。しかし、同じ麻(あさ)が、栽培植物としては、人類の主食となった小麦や米と同様、数千年前からメソポタミアやインドや中国といった古代文明発祥の地において盛んに栽培されてきた。日本では、江戸時代初期に木綿(cotton)栽培が全国に普及するまで、高級品である絹を除けば、麻がほとんど唯一の衣料品の原料であった。否、呉服地に限らず、袋・縄・網・草履をはじめ生活の多くの場で利用された。通気性の良い麻は、高温多湿の日本の風土に適していた植物繊維だったと言える。また、食用としては、栄養豊富な麻(お)の実は、七味唐辛子の材料によく使用されている。七味唐辛子には、辛さの主成分である唐辛子のすりつぶしたもの以外に、芥子(けし)の実、陳皮(ミカンの皮を乾燥させたもの)、胡麻、山椒、麻の実等が独特の風味を添えており、麺類や肉類を食する際の薬味として使用される。
こうして、麻は日本では盛んに栽培されたが、麻は生長の早い(炭酸ガスの吸収効率が高い)一年草で、今後は、地球温暖化防止のためにも栽培面積の拡大が望まれるが、同時に、その「麻薬」成分を常に発散しているが故に、栽培に携わる農家が「麻酔い」するとも言われている。因みに、20世紀の初め頃に、各国で麻の栽培が制限・監視されるようになるまでは、世界中で広く栽培されてきた植物である。
さて、日本ではこれらの麻の使い方以外に、もうひとつ大切な麻の使われ方があった。それは、神聖な場所を結界するために張り回される「注連縄(しめなわ)(「七五三縄」とも記す)」の素材(捻られた縄の部分)としての使われ方である。注連縄は、神社の入り口だけでなく、磐座(いわくら)や巨木に巻き付けられた。大相撲の最高位の力士の腰にも「横綱」と呼ばれる注連縄が巻かれている。また、個人の家の玄関や神棚や竈(かまど)にも張られている。正月などは、自家用車のフロントグリルにまで注連縄が張られている。それ以外にも、「大麻(おおぬさ)(「大幣」とも記す)」と呼ばれるお祓いをする時に神職が振る巨大なハタキ状(元来は薄く剥いだ麻の繊維そのものだったが、後に「紙垂(しで)」と呼ばれる紙が使われるようになった)の祭具や、玉串(たまぐし)と呼ばれる祭典時に神に奉奠(ほうてん)する榊の小枝に麻の繊維を結びつけた(元来は麻製であったが、紙や幣で代用)祭具が、神道では欠かすことのできない宗教儀礼に用いる道具である。なぜだか、これらの祭具類には麻を用いることになっている。
麻の繊維を取り去った後の茎の部分は「おがら」と呼ばれ、懐炉用の灰として用いられた。さらにこの灰は、お盆の迎え火や送り火を焚くときにも用いられる。つまり、麻という植物は、古来、日本人にとっては神聖な植物であって、その灰に至るまで、捨てるところのない完全なる植物なのである。であるからして、神道では「大麻」と書いて「おおぬさ」と読むことが一般的である。
▼ ありがた〜い「神宮大麻」
しかし、神道でも「大麻」と書いて、ズバリ「たいま」と読むケースがある。それは、伊勢の神宮から頒布される『天照皇大神宮』と記された神札(しんさつ=かみふだ)で、通常は「神宮大麻(じんぐうたいま)」あるいは、単に「大麻(たいま)」と呼ばれる。この『天照皇大神宮』と記された神札の霊験はあらたかということになっており、例えば、幕末に庶民を巻き込んで「ええじゃないか」の一大騒乱が巻き起こったときも、また、江戸時代の元和・慶安・宝永・明和・文政・天保の各年間、約60年周期で発生したとされる「おかげ参り」も、ある時、突然、伊勢神宮の御札(=「神宮大麻」)が空から振ってきたという事件がきっかけになって発生したと言われる。
いったん、「おかげ参り」が発生すると、わずか3〜5カ月の間に、300〜500万人が伊勢の神宮へ押し寄せたと記録されている。当時の日本の総人口から計算すれば、「5人に1人」というとんでもない高率になり、しかも、その大半が徒歩で伊勢の地を目指したのだから、各街道は蟻の行列の如き様であったと考えられる。その間、日頃は厳しい詮議があり、通行手形がないと通過できない各地の関所も、腰帯に柄杓(ひしゃく)を1本差して「おかげ参りじゃ」と言えばフリーパスとなり、街道沿いにある旅籠(はたご)や金持ちの屋敷で食事代を踏み倒しても罪に問われなかったといわれるくらいだから、国民全体が熱病でうなされたような異様な雰囲気だったと思われる。
現在でも、「神宮大麻」は、全国8万の神社を包括する宗教法人「神社本庁」の「本宗(ほんそう)」とされている「伊勢の神宮」(註:内宮と外宮の正宮をはじめとする125の別宮・摂社からなる神社の総称。「伊勢神宮」は通称で、正式には単に「神宮」と呼ばれるが、熱田神宮や明治神宮などと区別するために、本サイトとでは「伊勢の神宮」と呼ぶ)の大切な収入源となっており、7世紀末の天武・持統朝の古(いにしえ)より20年に一度繰り返し行われてきた式年遷宮の費用も、専らこの「神宮大麻」の頒布料(売上金)で賄われている。参考までに、その仕組みは、以下のとおりである。
▼ 大麻で稼ぐ伊勢の神宮
毎年、秋になると、伊勢の神宮から「(日本国民の)一家に一体」を目標にして、1,000万体の「神宮大麻」が東京都渋谷区代々木(明治神宮の広大な境内地に隣接。ただし、当の明治神宮は、路線の違いにより2004年に神社本庁の傘下から離脱した)にある神社本庁に下賜される。これを受けて神社本庁は各都道府県の「○○県神社庁」に、例年の実績に基づいて大麻を分配する。各県の神社庁は、県内の神社本庁に所属している神社(註:神社本庁と包括・被包括関係を結んでいない神社も結構ある。有名なところでは、明治神宮・靖国神社・伏見稲荷大社・日光東照宮などがある)に対して大麻を分配する。そのようなプロセスを経て、一般の氏子崇敬者が主に初詣の社頭で「神宮大麻」を授かる(購入する)ことになるのである。
この際、各神社においては、「神宮大麻」をいくらで頒布(販売)しても、そのこと自体は「宗教行為」なので構わないことになっている。もちろん、それぞれの神社独自の神札をセット販売しているケースが多いが、ここではテーマの「神宮大麻」の場合にだけついて説明する。「神宮大麻」の「メーカー希望小売価格(?)」は1枚800円である。なぜなら、各地方の氏神社ではなく、直接、伊勢の神宮へ参拝してその社頭で頒布を受けても1枚800円だからである。その800円の大麻を800円で頒布したのでは、各神社にとって神宮大麻を頒布する経済的メリットがない(もちろん、信仰上の問題だけを言えば、それでも一向に構わないのであるが、それだけでは、制度的に長年続かないであろう)。そこで、神社本庁では、800円の内の400円を伊勢の神宮へ上納し、残りの400円を「神徳宣揚費」という名称を付けて、手数料としてその1/3を神社本庁が、1/3を各県神社庁が、1/3を各神社が山分けする仕組みを構築している。つまり、「神宮大麻」が売れれば売れるほど、神社本庁と各県神社庁が儲かる仕組みになっているのである。
「1,000万体の頒布」を目標としていると書いたが、過去十年間の実績を見れば、900万体強である。もちろん、世俗社会の好況・不況の影響も受けるが、なんと言っても、式年遷宮が近づいてくると数字は伸びる傾向がある。何故なら、神宮大麻の頒布による収入は、20年に一度の式年遷宮の費用に充当されるからである。仮に1年間に、全国の各氏神社で頒布される合計数を900万体として計算すると、伊勢の神宮の「大麻」頒布による年収は、神社本庁を通じたルートでは、900万体X400円=36億円という計算になる。これに、直接、神宮に参拝した年間約500万人の2人の内1人が「大麻」を購入したとすれば、800円X250万体=2億円になるので、合計38億円ということになる。20年分だと38億円X20年=760億円になる。
同様に、神社本庁の「神徳宣揚費」という名の神宮大麻頒布手数料収入は、年間に900万体X400円÷3=12億円ということになる。8万の神社を傘下に収めていながら、年収12億円ということは、1神社当たり、たった15,000円しか「上納」していない計算になる。神社本庁は、本山が各末寺からの「賦課金や護持金」という上納金や、大僧正などの僧階の上昇と引き替えに徴収される費用によって運営されている伝統仏教各宗派とは、まったく集金構造が異なって(註:因みに、末寺の数が約1万寺の浄土真宗本願寺派の場合、年間の予算は一般会計だけで約100億円である)おり、この「神宮大麻」の頒布が全収入の9割を占めている。同様に、47都道府県の各神社庁も、合計で12億円(各県毎の多寡はあるが、平均すれば1県当たり2,500万円)の収入となる。
このように、普通の神社では「大麻」と書いて「おおぬさ」と読むときは、神道における重要な宗教儀礼である「祓い」に用いられる祭具(註:一般には、人々の身体に付いた穢れを祓い落とすための道具と理解されいる)であるが、「たいま」と読むときは、結構な金額を集金・上納していくという面もあり、不謹慎な言い方かもしれないが、麻薬の大麻との類比関係があるとも言える。
▼ 穢れを祓うのではなく、気を注入する
というよりも、そもそも「大麻」をはじめ、各種の向精神作用を持った天然植物由来の「麻薬」は、世界の諸文明において、太古の昔より、その特別な効能を期待して使用されてきたと断言しても構わない。御神酒(おみき)も祭典時の「神人共食(communion)」を通じて、共同体(community)に暮らす人々の一体感を盛り上げるために饗せられた一種の「麻薬」と言えなくもない。大麻(おおぬさ)で祓い清めるべき、「穢れ」とは、単なる「外在的な汚染」のことではなく、人間が本来その内部に秘めている精神的なエネルギーである“気(け)”が「枯れた」状態のことであり、大麻を頭を垂れた参拝者の頭上で振っているのは、その参拝者の「穢れ」を祓い取っているのではなく、むしろ、その参拝者に内在する「気エネルギー」を震撼させているのである。あたかも、炎を用いない電子レンジが、食品内部にある分子にマイクロウェーブを照射して振動させ、その分子が発する熱によって中から暖めるかのように…。
ここで、本論の冒頭で、時間を取って説明した「麻薬」の化学的な組成の話を思い出して欲しい。アヘン・モルヒネ・ヘロイン等の「麻薬」は皆、「アルカロイド系」の「神経伝達攪乱物質」だと述べた。また、ヒロポンやスピードやシャブなどの覚醒剤は、文字通り「中枢神経刺激物質」だと述べた。つまり、これを服用すると、頭脳が冴えて精神的にも肉体的にも仕事が捗(はかど)るのであるが、所詮は、その人間の体力のキャパシティは一定なので、薬効が切れた後の反動は大きいものがある。
例えば、1日平均4,000歩以上は歩かない私が、仮に覚醒剤を注射して興奮状態を創り出し、マラソン大会に出場して完走するようなものである。私が走る時の1歩の幅が1.5mだとすると、42kmは28,000歩で到達できる計算になる。つまり、通常なら1日に4,000歩しか歩かない私が、覚醒剤の興奮作用によって数時間で一気に42km=28,000歩を走破してしまったとしたら、その運動量は1週間分(28,000歩÷4,000歩=7)に相当するので、仮に完走できたとしても、私がそのことで失った体力を回復させるために、1週間泥のように眠りこけることになるというようなものである。このような事態が、教育や仕事の現場でたびたび起こったのでは、社会の安念秩序は保てない。しかも、依存症になりやすい。だから、覚醒剤は社会にとって害悪なのである。
▼ 大麻と釈迦の弟子
ところが、「大麻」については、若干、事情が異なる。まず、その化学的組成が、他の植物成分由来の麻薬で一般的な「アルカロイド(alkaloid)」系ではなく、THC(テトラヒドロカンアビノール)をはじめとする「カンナビノイド(cannabinoid)」系と呼ばれる高分子によって形成されている。カンナビノイドとアルカロイドの化学的組成の決定的な違いは、カンナビノイド系の化学物質はすべて炭素と酸素と水素の化合物(つまり、炭水化物や酒や酢と同じ)によって構成されており、窒素は含まれていない。つまり、植物毒の主成分であるアルカロイドではないということは、大麻が他の麻薬とは、決定的に異なる物質だということである。たしかに、大麻の主成分であるTHCは、人間の脳神経に強い幻覚作用をもたらすが、その強い鎮痛作用は、痛みに苦しむ末期癌の患者などへの投与は推奨されるべきものと考える。
また、脳神経系内でのカンナビノイドの受容体であるアナンダミド(anandamide)という物質は、「快感」に関する脳内麻薬物質であり、記憶・睡眠・摂食・鎮痛等の作用を司っている。ここで、この「アナンダミド」という化学物質の名前を見て気が付いた人は、相当な教養人である。アナンダミドはananda+amideという造語である。アミド(amide)は言うまでもなく、アミド結合はペプチド結合と共に最も一般的な高分子化合物の結合形式のひとつである。問題は、anandaである。Anandaは、釈迦の十大弟子の一人、アーナンダ(阿難尊者)のことである。釈迦の弟子の筆頭で、釈迦の入滅後、第一回の結集の議長を務め、仏教の第二祖となったMahakasyapa(摩訶迦葉)の弟子で、仏教の第三祖となった人物である。アーナンダは、法華経の世界では、釈迦の従兄弟であるにもかかわらず、悟りを開いた釈迦(仏陀)にことごとく逆らった悪人Devadatta(提婆達多)の弟ということになっている。
釈迦が成道(悟りを開く)した日に生まれたアーナンダは、彼の父である斛飯王(釈迦の父である浄飯王の弟)が、浄飯王に使者を送った時、浄飯王が大いに喜んで「アーナンダ(歓喜)」と名付けたと言われている。しかも、そのアナンダミドは、イスラエルのヘブライ大学において、チェコ人とアメリカ人の生化学者によって発見されたわけであるが、彼らがサンスクリット語の「歓喜(悦楽)」という意味を知って、この神経伝達物質に命名したというのであるから、驚きである。
▼ 大麻は神奈備である
もうここまで来たら、いちいち言うまでもあるまい。このアナンダミドに影響を与える大麻の主成分である「カンナビノイド(cannabinoid)」とはいったいどういう化学物質であろうか? cannnabin+oidであるが、oidはギリシャ語の接尾辞 (kind, type, species)という意味である。日本語で言えば、「○○類の」という意味である。英語で、「〜oid」で終わる単語を思い浮かべてみればよい。android
(アンドロイド)は、andro (人間)+oidであり、Mongoloid (モンゴロイド)は、Mongol
(モンゴル人)+oidである。因みに、アヘンなどの植物毒はalkaloid
(alkal+oid)である。そうすると、カンナビとはいったい何のことであろうか? 「神奈備(かんなび)」とは、神社などの背後にある神々が鎮まる神体山のことである。一番有名なのは、日本で最も古い神社と伝えられる大和国の大神(おおみわ)神社の神体山で三輪明神(大物主のカミ)が鎮まるとされ、現在でも禁足地になっている。
(kind, type, species)という意味である。日本語で言えば、「○○類の」という意味である。英語で、「〜oid」で終わる単語を思い浮かべてみればよい。android
(アンドロイド)は、andro (人間)+oidであり、Mongoloid (モンゴロイド)は、Mongol
(モンゴル人)+oidである。因みに、アヘンなどの植物毒はalkaloid
(alkal+oid)である。そうすると、カンナビとはいったい何のことであろうか? 「神奈備(かんなび)」とは、神社などの背後にある神々が鎮まる神体山のことである。一番有名なのは、日本で最も古い神社と伝えられる大和国の大神(おおみわ)神社の神体山で三輪明神(大物主のカミ)が鎮まるとされ、現在でも禁足地になっている。
「神奈備」とは、強いて言えば「神の居る場所」ということになる。たいていは、磐座(いわくら)や巨木であることが多いが、神霊(モノ)が依り憑ける依代(よりしろ) でさえあれば、人間や動植物や鉱物や人工物であっても一向に差し支えない。そして、これらの「もののけ(=モノの気)」の大親分が「大物主」であるとされる。人間の肉体や精神は、これらの「もののけ」が依り憑ける最高の依代なのである。そのために、日本人は太古の昔から、精神エネルギーを活性化するために「大麻(おおぬさ)」を振ってきたのであり、また、日本国家の総氏神である伊勢の神宮の「大麻(たいま)」を奉戴してきたのである。その意味では、麻薬の一種である「大麻」の主成分が、毒性を有する植物由来の神経伝達攪乱物質のアルカロイドではなく、カンナビノイドであることの意味は思っている以上に奥深いものがあると言えよう。