レルネット主幹 三宅善信
▼衝撃(shock)と畏怖(awe)?
2003年3月20日の昼前(日本時間)、アメリカ合衆国とその同盟軍によるイラクへの本格的な軍事攻撃がとうとう始まった。評論家の大方の事前予測では、開戦冒頭に大規模な空爆を集中し、圧倒的な軍事力の差を見せつけることによって、相手の戦意を削ぎ、一気に決着をつける作戦と言われていたが、開戦直前に突然持たらされたフセイン大統領の居場所に関する「確度の高い情報」によって、フセイン大統領とその息子たちおよびその政権の中核をなす人々を一挙に葬り去るため、巡航ミサイルによる一点集中ピンポイント攻撃となった。

奇襲攻撃を受けて炎上する大統領関連施設 |
この日の夕方7時のNHKニュースを視た中学1年生の長男が私に投げかけた質問によって、ハッとさせられた。このニュースというのは、巡航ミサイルによる奇襲攻撃によって火の手が上がるバグダッド市内の様子と、ペルシャ湾内にいるアメリカのミサイル巡洋艦から次々と巡航ミサイル「トマホーク」が発射される映像が、テレビの画面に二分割して映し出されている場面であったが、このシーンを視た息子が「お父さん、このミサイルを撃っている地点と、標的となっているバグダッドは、とても距離が離れているの?」と尋ねるので、私は、「なんでそう思うんや? ペルシャ湾からバグダッドまで1,000kmも離れていないので、巡航ミサイルの速度(600〜900km/h)だと、発射して1時間くらいで目標地点に到達すると思うけれど……」と言うと、息子が言った。「おかしいことない? ミサイルを発射している場所は周りが真っ暗なのに、着弾している場所は外の様子が明るいでぇ。1,000kmしか離れていなかったら、時差なんかほとんどないはずや。ということは、どちらかの画面が嘘じゃない?」と指摘されて、改めてハッと気が付いた。

米海軍艦船内のミサイル指揮所を
見学する三宅主幹 |
そうだ。テレビの画面の上に、「ライブ(生中継)」とスーパーが表示されているが、確かにおかしい。バグダッド市内の様子が24時間ライブ中継されているということは、ペルシャ湾の艦上から発射された巡航ミサイルは、実際には、少なくとも数時間前に発射されていたのをアメリカ軍が情報操作して、わざと数時間後に映像を配信してきたのである。なぜなら、マッハ20の猛スピードで飛んで(実際には真上から落ちて)くる弾道ミサイルとは異なり、たかだかジェット機の速度で飛行する巡航ミサイルの発射する瞬間をライブ中継すれば、よほどの素人でないかぎり何分後にミサイルが到達するか判ってしまい、予防措置(現在いる施設から退避するという意味)を取れてしまうからである。shock(衝撃)とawe(畏怖)を相手に与えるためには、何にもまして奇襲攻撃をかけねばならないのである。
▼結論が初めからあるアメリカの対外交渉
ところが、この戦争は、アメリカ中央軍の現地総司令官であるトミー・フランクス大将自身が最初の記者会見で述べたように、「shock
and surprise(驚き)」であった。実際の作戦を指揮する司令官にとっても、思いの外の作戦変更だったようである。すなわち、まさかいきなり自分の(潜伏場所が米軍に補足されていて)ところに飛んでこないだろうと思い込んでいたフセイン大統領を出し抜き、一挙に政権中枢部を抹殺しようとしたのである。
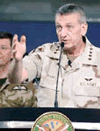
前線基地で記者会見を行う
フランクス総司令官 |
1941年12月7日朝(日本時間では12月8日)に、日本がハワイの真珠湾内の米軍基地を空爆したことが、太平洋戦争開戦の発端とされているが、当時アメリカは、これを「宣戦布告なき卑怯な奇襲攻撃」と罵しり、国内世論の沸騰を画策したが、フセイン大統領にしてみれば、ブッシュ大統領はアメリカ国内のテレビ演説で「48時間以内の武装解除もしくは、フセイン大統領の亡命」要求という最後通告(註:直接、イラクの外交機関には伝えていない)はしたものの、バグダッドへいきなりミサイルが飛んできたのであるから、宣戦布告のない「卑怯な攻撃」と言ってもよい。要は、結果として戦争に勝てば、それは卑怯な行為ではなくなり、負ければ、全ての行為は「不正義であった」と断ぜられるのである。これが、圧倒的な軍事力を有するアメリカの論理である。

奇襲攻撃で狙われた
フセイン大統領と息子たち |
今回の対イラク侵略戦争に至るまでの一連の国連安保理での交渉を見ていても判るように、アメリカには、まず「フセイン政権と戦争をする」という結論が先にあって、その後で、相手をむりやり戦争に引きずり込むためにはどうしたらいいかをこじつけているだけである。そして、相手に難しい要求を突きつけ、相手側がひとつでもその要求を受け入れたら、次々とハードな要求へとエスカレートさせてゆき、ついには、相手が絶対に呑めないような要求――例えば、「フセイン大統領の退陣」のような――を相手にふっかけ、相手に何がなんでも「戦争」という手段を選ばざるを得なくさせるのが、アメリカという国の常套手段なのである。「ならずもの国家」は、実はアメリカのほうであり、「悪の枢軸」とは、米英両国のことである。
たとえ、太平洋戦争開戦直前の1941年11月26日の段階で、日本政府に対してアメリカから出された無理難題(註:当時の国際常識からして、日本に突きつけられた『ハル・ノート』の内容がいかに無理難題であったかは、戦後、初めから敗戦国日本を悪者と決めつけて日本を処断した「東京裁判」においても、パール判事が「もし、アメリカが日本に送ったもの(『ハル・ノート』)と同一のものを他国へ通告していたとしたら、たとえその相手が地中海の小国モナコであったとしても、アメリカに対して自衛のために武力を以て立ち上っただろう」と言わさしめていることからも明白である)の書かれた『ハル・ノート』の要求を、日本がまるまる全部呑んでいたとしても、今度はさらにエスカレートした要求(例えば、国体の変更)と言ったような日本が絶対に呑めない条件を突きつけて、何がなんでも対日戦争に持ちこんでいたであろう。

不気味な侵略軍アメリカ兵の影 |
ことの善し悪しは別として、今回の米英両国による対イラク侵略戦争から、われわれ日本人は学ぶべき点が多くある。フランクス総司令官の記者会見でも、フランクス大将は決して「アメリカ軍」という言葉を使わずに、「Coalition
Forces(同盟軍)」という言葉を使い、世界に対して「この戦争はアメリカ一国がしているのではない」という形を演出したが、実際には、英国およびオーストラリア(前作『桃太郎バグダッドへ征く』で私が指摘したように、まさに「腹黒サクソン連合」による戦争であるが、実際は他の国はお飾りのように付いているだけで、実際に戦闘能力には圧倒的な差があるから、アメリカのお荷物以外の何ものでもない)をぶら下げながら戦争を始めたのである。
▼ ネオ・コンサバティブについて
さらに話を進めよう。日本における今回の対イラク戦争についての洪水的報道に当って、しばしば、アメリカの国際協調を無視した単独主義の根拠を説明する用語として、「ネオ・コンサバティブ(新保守主義)」という言葉がにわかにメディアを賑わすようになってきた。あるいは、政治家の中にもこのような流行語を口にする輩も目立ってきた。3月12日付の日経新聞の特集記事『結びあう信仰と政策』にも見られるように、ジョージ・ブッシュ氏個人の「Born
Again(再誕生)」という宗教的背景と政策決定の関係ということをようやく問題にするメディアも出てきたが、私から言わせれば、「何を今さら」という心境である。

三宅主幹ととても親しいと
噂されるウサン・クサイ氏 |
1998年の春に当レルネット誌上において、『主幹の主観』シリーズを立ち上げて以来、既に30本を越える作品群を私は『イスラム原理主義VS宗教国家アメリカ』シリーズで上梓して、今日の世界の危機的状況について警鐘を鳴らし続けてきた。その中で、私は、宗教国家アメリカという観点から、アメリカ合衆国の政治的意思決定、ひいては、それを背後で支えるアメリカ社会の集団的意志形成の背景に、「神に選ばれた国」、「新しいイスラエル」としてのアメリカ合衆国の宗教的動機づけが大きく影響しているということを指摘し続けてきたので、レルネットの読者諸氏には既にお馴染みの概念である。日本の政官業そしてメディア関係者諸氏も、もっと『主幹の主観』を読んで、勉強していただきたいものである。
このアメリカ合衆国という人口国家の宗教性という理解抜きには、米国の政治・経済・文化あらゆる価値判断の基盤を理解できないと断言しても過言ではない。「(自分たちとは原理原則の異なる)イスラム教を奉じる独裁政権が大量破壊兵器を保有することの危険性」という議論があるが、私から言わせば、世界最大の軍事力(註:アメリカ一国の軍事費は、第2位から20位までの諸国家の軍事費の合計よりも大きい)を誇り、人類を数回絶滅させ得るだけの大量破壊兵器を保有するアメリカ合衆国(の大統領や国民の多く)が、実は極めて偏った宗教(原理主義)的動機づけ――これを神学的には「福音主義(Evangelism)」と呼び、政治的には「新保守主義(Neo
Conservatism)」と呼ぶ――によって、その意思決定を行なっているということに、あまりにも無頓着な日本人が多いことのほうが、私にはshock
and surprise(衝撃と驚き)である。
▼神の高みに立ってフセインを断罪
アメリカにおける福音主義という宗教右派(註:米国大統領選挙における宗教右派の影響については、2000年の3月に上梓した『宗教右派:大統領選挙に見るアメリカ人の宗教意識』において、ブッシュ氏が大統領に当選するための条件について詳しく分析しているので、ご一読されたい)とネオ・コンサバティブを繋ぐキーは「一極主義」である。自らが奉ずる価値のみが絶対的な真理であって、他の価値の存在を認めようとしないのは、イスラム原理主義も同じことである。1998年の8月に『正義という不正義』で論じたように、私は「そもそも正義というものが存在すると想定すること自体に、他者を自己の価値判断によって断罪するというに不遜な姿勢が現れるのである」と断じたのはそのことである。
今回のアメリカの行動は、実は、既に2002年10月10日の時点で、決定的な方向づけがなされていた。フセイン政権を目の仇にするジョージ・W・ブッシュ米国大統領は、昨年の10月10日、上下両院から「イラクを武装解除、すなわちフセイン大統領を追放すること」についての全権委任を巧妙に取り付けたのである。その4週間後の11月5日に行なわれた中間選挙において、ブッシュ政権による2001年9月11日のいわゆる「同時テロ」事件と結び付けた政治的プロパガンダが、単純なアメリカ市民の心情を見事に掴んで、上下両院共に、ブッシュ大統領の共和党が多数派を占めるという政治状況がもたらされた。その余勢を駆ったブッシュ政権は、そのわずか3日後の11月8日に、今度は国連安保理において、イラクに対して、無期限無条件の査察の実施と大量破壊兵器の廃棄を求める決議(いわゆる『安保理決議1441号』)を全会一致で採択させることに成功した。
アメリカにとって必要である政治的法的手続きはここまでである。すなわち、アメリカ合衆国の国民から全権委任を受け、国連安保理からも全会一致を取り付けたブッシュ政権は、いわば、神の高みに立って「独裁者」サダム・フセインを断罪する権利を手に入れたのである。それ以後の国連を舞台にした様々な駆け引き、フランスやロシアの抵抗は、アメリカによって仕組まれた国連そのものを無力化させるための通過儀礼にすぎなかったのである。
▼政権が親米の国は、国民が反米
これまで、アメリカは「民主主義」という類似宗教を世界に普及させるために、かつて、ソビエト連邦が「共産主義」という擬似宗教を世界に布教させるためにはどのような手段を執ってもよいと思っていた(註:自分たちの行なっている布教行為=改宗の強要が、(真理に気づかずに苦しんでいる)「相手を助けてあげるため」と確信しているという点で、宗教的伝道と軌を一にしているので、私はこれらを擬似宗教と呼んでいる)のと同じように、国際社会において振る舞ってきたが、その論理は、実は矛盾に満ちたものであった。ある時は、共産主義への防波堤として、アジア・アフリカ・中南米の各地域において、極めて非民主的な独裁権力と結びつき、ドミノ倒し的共産化革命の拡大を防ごうとしてきたことは、今さら言うまでもない。腐敗しきった南ベトナムのグエン・バン・チュー政権を支援し続けてベトコンと戦わせ、韓国においては、イ・スンマン(李承晩)政権、パク・チェンヒ(朴正熙)政権と軍事独裁政権を支援し続けてきたし、他にも、フィリピンにおけるマルコス政権、インドネシアにおけるスハルト政権と、このような例を探せば、枚挙に暇がない。
というわけで、アメリカは以前から、その政権が親米でありさえすれば、たとえ独裁政権であったとしても、これを認知してきた(註:天下人である秀吉や家康に「所領安堵」してもらうことによって、自己の地域支配の正当性を担保しようとした封建諸侯と天下人との関係と類似性を有している)。ここに、「自由と民主主義を世界に広めるため」という表向きアメリカ教が説く教義の欺瞞性が見て取れる。また、世界の多くの国で共通して言えることは、その政権が――その国が共産主義国家であれ、イスラム教国家であれ――政権の中枢部が親米である場合は、大多数の国民が反米であることが多く、また逆に――かつてのソ連や東欧社会主義諸国のように――政権が反米を唱えている国では、国民は密かに親米(少なくとも、アメリカの自由で豊かな物質文明に憧れを抱いて、ハンバーガーやジーンズを買い求めたりする)であることが多い。

世界各地で起こった反戦・反米デモ |
この図式を中東社会に当て填めてみると、中東最大の人口を有する親米政権であったイランのパーレビ王朝は、その石油資源から得られるによる潤沢な収入によって欧米型の豊かな消費生活を社会に広く採用し――秘密警察を使った強権的な性格を持つ政権ではあったが――世俗的な(脱イスラム法的な)国家運営を進めていたが、1979年にシーア派の大アヤトラ(宗教的指導者)ホメイニ師が亡命先のフランスから帰国して「イスラム革命」が起こり、パーレビ王朝が崩壊。シャーの圧政への反感がそれを背後から支援してきたアメリカへと向かい、アメリカ大使館占拠事件が起きるということによって、国民のムードは一挙にシーア派原理主義回帰へと傾いた。この事件がアメリカの中東戦略崩壊の第一歩となった。(註:この事件は、米国の政治にも大きな影響を与え、「中東和平」推進派のカーター政権から「力の外交」と標榜するレーガン政権へと以降した)。
そして、新たに反米国家となったイランと隣接し、イランの「国教」ともいえるシーア派住民を南部に数多く抱えて、「シーア派革命」の伝染を恐れたイラクのフセイン政権とイランのホメイニ政権とが鋭く対立するイラン・イラク戦争が始まると、アメリカのレーガン政権は「イラン憎し」の一点から、フセイン政権に大量の武器および経済援助を実施したのである(註:アメリカの外交政策の基本理念は「敵の敵は味方」という論理である)。現在、フセイン政権打倒の急先鋒ラムズフェルド国防長官なども、当時はバグダッドを訪れ、友軍フセイン大統領と親しく会見したりもしている。
この8年間におよぶイラン・イラク戦争において、国力でも軍事力でも劣るイラクが、一応、負けでない形で決着できたのは、とりもなおさずアメリカのおかげである。ただし、1990年代に入り、イラクが隣接する豊かな小国クウェート(地図を見てもらったら判るように、「クウェートは、もともとイラクの一県に過ぎない」というフセイン大統領の説にも一理ある)を侵略すると、国際社会は一致団結してこれに対抗して多国籍軍を構成し、フセイン政権の野望を撃破した。というのも、「正義」云々というよりも、石油の安定供給と、クウェートの次には世界最大の産油国サウジアラビアが控えていたからである。
▼湾岸の親米王政をどう評価するか
しかし、多国籍軍を構成した欧米諸国が自らの犠牲を払って守ったクウェートという小国は、ジャビル首長一族が支配する個人商店的独裁国家であり、物質的には豊かであるが、クウェートには、議会も選挙もなく、途上国出身の労働者を二級市民としているとんでもない国である。また、聖地メッカの守護者を自認するサウジアラビアも、ワッハーブ派というイスラム原理主義を国教とする独裁国家であり、国家の名称が示すようにサウド王家が莫大な石油収入という富を独占的に支配する前近代的部族国家であり、もちろん選挙も議会もない。国王が首相を兼ね、皇太子が外相を兼ねるという個人商店的独裁国家である。これらの独裁王政が、国際社会において「所領安堵」されているのは、とりもなおさず、親米という一点で、アメリカから庇護されているからである。ところが一部で不正が行なわれているに違いない(註:「支持率100%」ということはありえないが、もしこれが不正選挙というのなら、いずれも「支持率97〜99%」の社会主義諸国の選挙も、すべてインチキということになる)であろうが、それでも、一応は、選挙で選ばれた民主的なフセイン政権のほうが、反米であるという一点により、アメリカから軍事攻撃を受けているのである。「世界に自由と民主主義を広める」というアメリカのお題目が、いかに自分勝手でインチキ臭いものであるかは明白である。
ご存知、アルカイダの首領様であるビン・ラディン氏は、サウジアラビア有数の資産家の息子であるだけでなく、世界中の多くのイスラム原理主義運動に対し、サウジ王家は、裏から資金援助を行なっている。旧ソ連邦が1979年にアフガニスタンに侵攻した時、イスラム国家の共産化を恐れたサウジ王家は――その数年前に起きた『オイルショック』(註:石油の消費者である先進国側から言えばオイルショックであるが、産油国側から言えば、これまで必要以上に廉価で先進国に供給させられていた原油を適正価格で売ったまでのこと)で得た――潤沢な資金を、アフガニスタンやパキスタンのイスラム原理主義活動家に提供し、各地に神学校を樹立し、その結果として、彼らがタリバンをはじめとする原理主義政権を確立して、ソ連の対抗し得たのである。彼らはイスラム教を奉じて異教徒と戦う「聖戦士(ムジャヘディーン)」と呼ばれたのである。

いつも意見集約のできない
アラブ首脳会議 |
この、「自分たちに協力する勢力であれば、たとえそれが独裁者でも、その政権と組む」というアメリカの基本的な政治方針にとって、中東の要は長年サウジアラビアであった。今でも、サウジにはアメリカ軍が駐留している。「聖地の守護者」を自認するサウジアラビアの本音は、厳格なイスラム教的模範に基づくイスラム革命(註:一部の王族が富を独占するというような体制は、本来のイスラムの教義からは許されない)がイランから波及することを恐れ、過去20年間にわたって「イスラム革命封じ込め」政策を進めてきたが、まさにその一点において、アメリカと利害が共通していたのであり、また、世界一のエネルギー浪費国(註:それ故、『温暖化防止条約』の国際的枠組みからも自分勝手に離脱した)であるアメリカが必要とする原油価格が上がり過ぎないように、OPEC(石油輸出国機構)の最大メンバーであるサウジが、アメリカの利益を代弁して石油価格高騰に歯止めをかけてきたのである。
▼9.11が変えた米国のサウジへの姿勢
しかし、2001年9月11日の米国でのいわゆる「同時テロ」事件から状況は一変した。世界最強の軍事大国アメリカに面と向かって反旗を翻してきた(と、米国が決めつけた)アルカイダのバックにはサウジアラビアの影があり、この独裁国家(註:苛酷な肉体労働等は、パキスタンやバングラデッシュといった同じイスラム教国でも貧しい国からの出稼ぎ労働者に押し付け、しかも、彼らは「ニ級市民」として、国民としての基本的な法的権利すら与えずに、自分たちだけの物質的繁栄を謳歌してきたサウジアラビア)に対して向けられるようになったのである。今回の対イラク侵略戦争で、米軍入陸の足場となったクウェート(註:13年前、イラクに国土を蹂躪されたクウェートのみが国家在立の安全保障上の担保を米国に依存しているので喜んで米軍を受け入れた)を除くサウジ、カタール、バーレーン、アラブ首長国連邦等の湾岸君主諸国の対イラク戦争に対する協力姿勢が湾岸戦争の時と比べて、態度が曖昧なのはここに原因がある。
アラブの専制君主諸国は、一方で、「所領安堵(現状維持)」を担保してもらうために、アメリカへの見せかけの忠誠心を示しながら、なおかつそのことは、国民の大多数を占めるイスラム教徒からの反感を招き、かといって、国民の大多数を占めるイスラム教徒の反米の声に従えば、アメリカの軍事力によって政権解体へと追い込まれることは必然であり、どちらの道を厳選しても、体制維持が極めて難しい。今回の対イラク戦争において、ブッシュ大統領は「イラクに欧米型の民主主義を確立し、これを足がかりに、中東のイスラム教原理主義に根ざしたアラブ人による専制君主制政権に変化をもたらし、もって『パレスチナ・イスラエル問題』に活路を開く」という都合のいいことを言っているが、そのようなことを本心から望んでいる中東諸国なんぞもちろんない。
さらに、「パレスチナ・イスラエル問題」に関連して言えば、今回の米英軍によるイラク攻撃の表向きの理由が、1991年の湾岸戦争終結以来のの長年にわたる国連の決議をイラクが無視し続けてきたので、これに従わせるためというのなら、長年にわたって国連(による占領地域からの撤退要請)決議を無視して、パレスチナを軍事的に占領し続けてきたイスラエルに対して、どうして「国連の決議に従わせる」と言って、これを攻撃しないのか? 同じ国連決議違反をしても、イスラエルの場合にはイスラエルの味方に付き、国連決議を堂々と無視しておいて、一方で「国連決議に従わせる」という理由でイラクを攻撃するという自分勝手なダブルスタンダードの政策をアメリカが取り続けている限り、世界がアメリカの中東政策を信頼しないことは明らかである。
アラブ人とユダヤ人に対する英国による『バルフォア宣言』の二重約束に基づくイスラエルの建国そのものに違法性があったのであるから、「新しいイスラエル」を自認するアメリカ合衆国は、パレスチナの地にある現在のイスラエル共和国を一旦解散して、この土地をパレスチナ人に返し、テキサスかアリゾナ州あたりの誰も住んでいない砂漠地帯に、イスラエル共和国を新たに作らせてあげればいいのである。アメリカ人お得意のテーマパークよろしく、「嘆きの壁」をはじめとしてエルサレムそっくりの街や、塩をしっかりと溶かし込んだ「死海」なども再現するばよい。それが、最も早い「パレスチナ・イスラエル問題の解決であるとすら、私は思う。
最後に、今回の戦争に突き進んだアメリカのイラクに対する法外な要求の数々と、イラクのフセイン政権が示した反応――特に、開戦翌日にフセイン大統領が健在を示すために行なった演説――を聞いて、私は、1941年の12月8日に布告された心ならずも対米英戦争へ踏み切らなければならなかった『宣戦の詔勅』の文章を思い起こした。あの時(『ハル・ノート』による最後通牒)、日本がむりやり太平洋戦争へ引きずりこまれた経緯と、今回のアメリカの手法がよく似ているので、改めて読み直されることをお薦めする。
参考資料:『宣戦の詔勅』
天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本帝国天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス
朕茲ニ米国及英国ニ対シテ戦ヲ宣ス朕カ陸海将兵ハ全力ヲ奮テ交戦ニ従事シ朕カ百僚有司ハ励精職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ尽シ億兆一心国家ノ総力ヲ挙ケテ征戦ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ
抑々東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄与スルハ丕顕ナル皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列国トノ交誼ヲ篤クシ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ之亦帝国カ常ニ国交ノ要義ト為ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端ヲ開クニ至ル洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民国政府曩ニ帝国ノ真意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ東亜ヲ平和ヲ攪乱シ遂ニ帝国ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有余ヲ経タリ幸ニ国民政府更新スルアリ帝国ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ残存スル政権ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ相鬩クヲ悛メス米英両国ハ残存政権ヲ支援シテ東亜ノ禍乱ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞ウセムトス剰ヘ与国ヲ誘ヒ帝国ノ周辺ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ更ニ帝国ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ与ヘ遂ニ経済断交ヲ敢テシ帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ回復セシメムトシ隠忍久シキニ弥リタルモ彼ハ毫モ交譲ノ精神ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ益々経済上軍事上ノ脅威ヲ増大シ以テ我ヲ屈従セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝国ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破砕スルノ外ナキナリ
皇祖皇宗ノ神霊上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亜永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス
御名御璽 昭和十六年十二月八日