レルネット主幹 三宅善信
▼イラク攻撃で大量破壊兵器は使用されるか
イスラム教原理主義政権タリバンが実行支配していたアフガニスタンの首都カブール「解放」1周年のこの日、前日のイラク国民議会の「国連安保理による大量破壊兵器査察受け入れ拒否決議」を受けて(註:最終的には、「慈悲深く、慈愛普く」サダム・フセイン大統領が「アメリカの理不尽な要求は受け入れがたいが、国民の生命の安全には代えられない」といったごもっともな理由を付けて、「耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで」で、査察の受諾表明を行うと予想されるが、たとえ査察を受け入れたとしても、理由はどうあれ、「フセイン憎し」で凝り固まるジョージ・W・ブッシュ米国大統領は、追加的になんやかやと、イラクが受け入れられない「難癖」を付けて、最終的にはイラク攻撃を行うと予想される)、アメリカによるイラク攻撃が秒読み段階に入った。そんな折も折、不気味なニュースが飛び込んできた。
外電によると、「先頃、イラクがトルコで、100万人分の毒ガス解毒剤と脚への自家接種用の注射キットとを一緒に購入しようとした」というのである。このことから連想されるのは、以下のストーリーである。制空能力では圧倒的な優位を誇る米英軍といえども、巡航ミサイルや爆撃機でイラクの軍事施設や通信・運輸・油田等のインフラを破壊しただけでは「戦争に勝つ」ことはできず(註:12年前の湾岸戦争の際に、空爆で圧倒しながら、地上軍を首都バグダッドまで進めて「占領」しなかった父ブッシュ大統領が、結局はフセイン政権を打倒できなかったことが良い例である)、最終的には、自軍にも相当の死傷者が出る「地上戦」を行わなければ決定的な勝利(フセイン政権の打倒)は得られないことは明白である。また、その地上戦こそ、フセイン政権の「望むところ」である。ゲリラ戦が中心となったベトナム戦争で懲りたアメリカ軍は、それ以後、ほとんど地上戦を行ったことがない。もっぱら、自らの「死」を意識しなくて済む「飛び道具」によるハイテク戦ばかりである。映像メディアが発達した今日、戦死した米軍兵の遺体が次々とアーリントン墓地へ埋葬され、また、傷ついた女子供といったイラク一般市民の映像がテレビで流されれば、アメリカ国民の厭戦気分は一気に高まり、一方、全世界のイスラム教徒のジハード(聖戦)意識は、いやが上にも盛り上がり、世界各地でアメリカ人および、その同盟国の人々を狙ったテロ事件が続発するであろう。
その地上戦においても、初戦では、陸海空一体となった米軍のハイテク攻撃が優勢になることは間違いない。しかし、イラク軍の「飛び道具」が叩かれ、いざバグダッドへ進軍する段になり、兵と兵がお互いの顔の見える距離に近づいて白兵戦の様相を呈した時、かなりの確率で「貧者の核(Atomic)兵器」と呼ばれる「生物(Biological)化学(Chemical)兵器」が使用されるであろう。昨年秋の米国での炭疽菌騒動からも判るように、衛生状況の良い(免疫がつかない)先進国で暮らす人々(特に若者)には、天然痘や炭疽菌といった生物兵器が有効なことは証明済みである。しかも、医療が不十分な貧しい途上国に暮らす自分たちには、ある程度、自然に免疫がある(註:というより、菌に弱い人はもう既に死んでしまっており、結果的に生き残っている人は免疫が付いていると考える)と考えられる。さらに、湾岸戦争の際にも、自国内の少数民族クルド人を掃討するためにサリンやVXといった毒ガス兵器を使用し、この有効性も実証済みである。したがって、至近距離の地上戦においては彼我の武器の劣勢を補うためにBC兵器を使用するであろう。そのためには、自軍の将兵に「解毒剤の投与」は必須条件である。それが、今回、イラクが解毒剤を大量購入しようとした理由である。
今回の対イラク戦での米軍が投入を予定している兵力は20〜25万人の大規模に及ぶもので、戦費は2,000億ドル(約25兆円)の巨費に登る。専門の研究機関によると、犠牲者数はイラク兵や一般市民を中心に50万人にもなるそうである。もし、BC兵器を用いた戦闘で相当数の犠牲者が米軍に出、逆上した米軍が戦術核など使ってしまったら、それこそ犠牲者数は400万人にも登るという半世紀ぶりの大戦争になってしまう。そんな危険まで冒してアメリカがイラクにこだわるのは、この湾岸地域における覇権の維持が、西側諸国の石油の確保(註:西側諸国の利益のためではないことは言うまでもない。米国が西側諸国への石油の分配権を握っている現在の世界秩序の維持のためである)にとって最重要な課題であるからである。ブッシュ親子がテキサスの石油資本のオーナーであることもそれに一層の拍車をかけている。要は、「石油を誰が支配するのか」ということなのである。
▼コーカサス地方を支配するのは誰か
日本では、これまであまり注目されてこなかったけれど、石油埋蔵量の多い地域として、現在、世界的に注目されている地域がある。カスピ海とアラル海沿岸の中央アジア地域である。かつて、この地域は「ソビエト連邦」の(構成共和国)一部であったが、1991年のソ連邦崩壊に際して、アラル海より東にあるイスラム系の比較的規模の大きい中央アジア5カ国(カザフスタン・トルクメニスタン・キルギスタン・ウズベキスタン・タジキスタン)が民族別に独立したが、これらの国の政権は安定しており、かつてのソ連邦の「盟主」ロシアとの関係も比較的安定していた。ところが、南をイランとトルコに接し、カスピ海と黒海の間に位置する3つの小国、すなわち、グルジア・アルメニア・アゼルバイジャンのいわゆる「コーカサス」あるいは「ダゲスタン」地方と呼ばれている地域が問題となった。
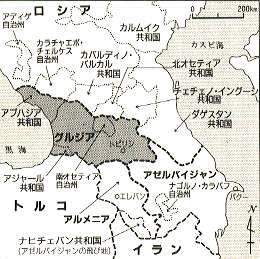
モザイクのようなコーカサス地方の民族分布 |
この辺りは、旧約聖書『創世記』に登場する「ノアの方舟」が大洪水後に着岸した「最初の陸地」アララット山という話にも出てくるように、非常に古くから、ユダヤ・キリスト・イスラム教といったアブラハムの宗教にとっては縁の深い地域である。また、それだけ、ごく限られた地域内にモザイクのごとく、いろな宗教に属する人々が居住している。しかも、嶮しい山々を越えて、いろんな民族が往来している。したがって、民族的・宗教的に覇権を握ろうとする連中が跳梁跋扈しがちである。ソ連邦崩壊の際にも、コーカサス地方3国の「独立」を認めたロシアも、それらの3カ国に隣接するダゲスタン共和国やチェチェン・イングーシ共和国他の小国の「独立」は認めず、ロシア連邦を構成する「連邦内共和国」として留まるように命じた。おまけに、「独立」を許されたアゼルバイジャン共和国の中にも、「共和国内共和国」とも呼ぶことができる少数民族によるナゴルノ・カラバフ自治州やグルジア共和国内のアブハジア共和国といった「入れ子細工的」悪循環が起き、政治的には極めて不安定な様相(ある意味の内戦状態)を呈している。これらの社会不安と貧困につけ込んで勢力を伸ばしてきたのが、アルカイダを始めとするいわゆる国際的「イスラム原理主義」勢力である。
ご承知のように、10年前までは、これらの地域は、ソ連の一部であったし、ソ連邦崩壊後も、いわば「ロシアの前庭」のような地政学的な位置づけから、豊富な石油埋蔵量があるにもかかわらず、国際的には手を付けることができにくい地域であったことは事実である。アメリカをはじめとする西側G7諸国としても、石油資源の湾岸地域への過度の依存は、安全保障上望ましくないことは明白であったが、上記のような理由から、なかなかカスピ海沿岸地域へのコミットはしにくい状態にあった。なにしろ、ペルシャ湾岸地域のように、公海に面していないので、採掘した原油は必ずパイプラインを通してなければ外部へ持ち出せない。だからといって、イランやイラク領内を通過するコースはあまりにも無謀である。アメリカからみれば、北朝鮮と共に「悪の枢軸」に挙げられているこれらの国を通過するパイプラインなんて実現不可能である。当然、ロシアは、ロシア連邦内のダゲスタン共和国やチェチェン共和国を通るパイプラインのルートを延伸して、これを直接、西ヨーロッパの消費地へ繋ぎたいと考えるだろう。それゆえ、決してチェチェン共和国の連邦からの独立は認めないだろう。
一方、アメリカは、グルジア・アルメニア・アゼルバイジャンの3カ国へ手を突っ込んで、自分たちの陣営に引き入れ、イスラム教国であるにもかかわらず、既にNATOの忠実なメンバー(西側への忠誠の証として、いつも中東地域に出撃する米軍への基地に提供を強要されられている)となったトルコを横断して地中海へ出るパイルラインの建設を図っている。もちろん、そのパイプラインは、カスピ海をも横断して、中央アジアの5カ国へも延伸してゆく予定だ。そうなっては、まるっきり、ロシアのアドバンテージはなくなるので、ロシアも絶対にそれを阻もうとするであろう。どちらも受け入れがたいイスラム原理主義国家の拡大の阻止と、アメリカの影響力の拡大の阻止の2つの要素が重なって、ロシアはここ数年、チェチェンに対して厳しい態度を取ってきた。この辺りの詳しい経緯については、3年前に私がコーディネートした大阪国際宗教同志会の例会で、元ロシア連邦大阪総領事のG・コマロフスキー氏が『イスラム原理主義の挑戦を受けるロシア』と題する講演でたいへん解りやすく述べているので、ご一読いただきたい。
▼対チェチェン強攻策でプーチンが表舞台に登場
アメリカにおいては、貧しい南イタリアのシシリー島出身の人々がギャング団(マフィア)を結成していると信じられているように、ロシア(特に、首都モスクワでは)においては、良からぬことをするギャング団の連中は大抵、チェチェン出身者であると信じられている。このような社会背景のある中で、1998年8月、市場経済への移行が順調に進まず、70年間にわたる社会主義経済の後遺症とも言える「法人税の滞納」と「資本の海外流失」に悩まされていたロシアが金融危機に陥り、ロシア政府(エリツィン政権)はとうとう一方的な「海外債務の支払い停止」を宣言し、デフォルト状態になった。この社会混乱に乗じて、「独立」を画策するチェチェン人たちが、8月31日、政府関連施設を狙った爆破テロ事件を起こしたのである。この緊急事態に、迷走するエリツィン政権の救世主として登場したのが、先の月にFSB(連邦保安局=旧KGB)長官に就任したばかりのV・プーチンであった。
この時、チェチェン人のテロリスト集団を動かしていたのは、アフガニスタンのアルカイダから派遣されたオマル・ハッターブ司令官であった。これまでも、ロシア軍はチェチェン共和国に対して攻撃を繰り返していたが、いかにも官僚的な随時投入であり、また、ソ連崩壊以来、自信喪失して志気の下がっていたロシア軍では、80年代のアフガン抵抗戦争以来の歴戦の強者には決定的な打撃を与えることができなかった。そこへ颯爽と登場したのが、共産党政権時代、旧東ドイツでスパイ活動を行っていた現実主義者のプーチンFSB長官であった。プーチンは、チェチェン人の資金源を絶つために、主に石油関連施設を徹底的に攻撃し、大きな成果を挙げて、ロシア市民から喝采を受けた。これに対して、チェチェン人たちも9月9日に、モスクワの一般市民の暮らすアパートで爆弾テロを行い、死者92名を出す惨事となったが、プーチンの巧みな世論操作により、ロシア国内では「チェチェン人性悪説」(註:つまり、「悪者退治」のためには、民族自体がテロリスト集団であるチェチェンの一般市民を巻き込んだ強硬な掃討作戦を行っても許されるという考え方)が定着した。
折しも、この年の11月にエリツィン大統領が体調を崩して入院するという事態が生じ、以前から「次ぎ」を狙っていたプリマコフ首相がエリツィン大統領派の追い落としを画策し、市場経済化と共に生まれた新興財閥や警察権力を巻き込んだ権力闘争へと発展したが、プーチンFSB長官の多大な功績によってエリツィン大統領派が勝利を収め、その論功行賞として、チェチェン介入から1年目の1999年8月9日、遂に、プーチンが首相に任命されたのである。エリツィン大統領の絶大なる信頼の下、首相になったプーチンは、「ポスト・エリツィン」を視座に入れて、エリツィンへの忠誠を尽くすように見せながらも、自らの国民的人気を不動のものとするため、就任後わずか4日目の8月13日にチェチェンへの本格的なロシア連邦軍の投入を行った。
日本人的な感覚から言えば、ゴルバチョフのような理性的な指導者のほうが好ましく見えるのであるが、ロシア人の気質はどうやら、少々荒っぽい手段を使っても良いから強靱な指導者を好むようである。しかも、当時の米ロの指導者を比較しても、若々しいクリントン大統領と比べて、野暮ったいヨボヨボのアル中親爺のエリツィン大統領では、あまりにも「見栄え」が悪く、依然として「大国意識」だけは強いロシア人は、なんとかして欲しいと思っていたに違いない。そこに、クールなプーチンが登場したのである。プーチンの作戦はまんまと成功した。この辺りの経緯は、拙作『「ヤマトの諸君」:プーチン首相の正体』をご一読いただければ幸いである。
ロシアの若き指導者プーチン首相の国際社会へのデビューはすぐに訪れた。ニュージーランドで開催されたAPEC(アジア太平洋経済協力機構)の首脳会議である。1999年9月11日、APEC首脳会議の席上、プーチン首相は、オサマ・ビン・ラディン氏を名指しして対テロリスト強攻策を宣言。西側諸国の一員として、欧米諸国と共同歩調を取るポーズを見せた。もちろん、プーチンの本当の狙いは、これまで欧米社会において根強くあった「チェチェン人たちの民族独立要求は正当な権利であり、ロシアの対チェチェン強攻策は人権軽視だ」という声を封じ込めることである。このプーチンの発言に真っ先に反応したのは、そのわずか2日後にモスクワで犠牲者116人の惨事となったアパート爆破テロ事件である。プーチンは、APEC会議を切り上げて、急遽帰国し、実質的に国家の全権を掌握して対チェチェン戦争に取り組んだ。このプーチンの「オサマ・ビン・ラディン批判」から、ちょうど丸2年後の2001年9月11日に、米国での「同時多発テロ」事件が勃発するのである。
▼モスクワ劇場占拠事件と毒ガスの威力
しかし、「9.11同時多発テロ」事件は、プーチン大統領の計画(大国ロシアの威信回復)も大いに狂わせた。これまで、自他共に「ロシアの前庭」と思われていた中央アジア5カ国の内、ウズベキスタンやカザフスタンが、米国に対して「対タリバン戦争のための基地を提供する」と、テロ事件発生後わずか3日という早さで宣言してしまったのである。ロシアの面子は丸つぶれである。冷戦時代なら想像も付かなかった中央アジアに米軍部隊が展開するという様相を呈した。「人類の敵」ビン・ラディンをやっつけるという大義名分でやりたい放題のアメリカと、このアメリカに「貸し」を作って経済援助を引き出し、同時に、「元」宗主国のロシアに対する交渉カードにしようという意図見え見えであった。1979年12月のソ連軍による電撃的アフガン侵攻作戦は、国威宣揚を目指した社会主義圏初のモスクワ・オリンピックが西側諸国からボイコットされただけでなく、一時的にせよ、アフガニスタンが「ソ連化」したために、アフガンにいるイスラム原理主義者が大量にソ連内に流入し、結果的には、10年後のベルリンの壁崩壊に始まるソ連邦の解体の引き金まで引いてしまうという大誤算となったが、今また、米国の中央アジア支配にまで及んでしまった。
それ以来、チェチェンにおいても、アルカイダをはじめとするイスラム原理主義勢力が跋扈し、ロシアの心臓部であるモスクワでの相次ぐテロ事件となった。なかでも、犠牲者の数からも、また、ロシア内外に与えた衝撃の大きさからでも群を抜いていたのが、この10月23日にモスクワで発生した劇場占拠事件である。チェチェン人武装集団がモスクワ市内の劇場を占拠し、一部の外国人を含む約700人を人質に取ったのである。この事件は、発生後わずか3日後にして(もっとじらして犯人グループを疲れさせるという手もあると思われる)、26日のロシア治安部隊の強行突入によって、120人もの犠牲者を出して鎮圧されたのである。
しかも、ロシア治安部隊は、犯人グループの抵抗力を奪うため、「突入」に先だって換気ダクトからアヘンを基にした麻酔薬「フェンタニール」を流し込み、「救出」作戦を実行した。しかし、700名の内、犯人や治安部隊の発射した弾丸に当たって亡くなったのは、わずか2人だけで、外国人を含む120人の一般市民の人質たちは、ロシア治安部隊の手によって「殺された」のである。事件から2週間以上が経過した現在でも150人が入院しているそうだ。これでは、決して、救出作戦が「成功した」とは言えまい。「麻酔ガス」ですら、これだけの「効果」があるのである。もし、サリンやVXなどの「毒ガス」なら、その殺傷力は比べものにならないであろう。つまり、言葉を換えれば、実践での化学兵器の有効性がいみじくも証明されてしまったのである。

久々にニュースの表舞台に登場した
ビン・ラディン氏 |
米軍との地上戦が不可避とされるイラクの指導部や、「その次」と名指しされている北朝鮮の指導部が、あらためて、毒ガスをはじめとする化学兵器に威力に注目したこと請け合いである。そうこうしているうちに、もっと不気味なメッセージが、中東カタールの衛星ニュース局アル・ジャジーラに寄せられた。1年以上に及ぶアメリカによるアフガニスタンへの絨毯爆撃と、血眼になった捜査にもかかわらず、遂に捕まえられなかったオサマ・ビン・ラディン氏から、この秋、世界各地で起こったテロ事件を称賛し、ひとりアメリカだけでなく、独・仏・伊・加・豪などを名指しにした新たなテロ攻撃の予告されていたのである。イスラム原理主義者と欧米資本主義との戦争はまだ始まったばかりである。ロシアも「漁夫の利」の狙って、この戦いに巧く乗じて、「失った威信」の回復を着々と図っている。それにしても、「情けない」というか「ラッキー」を言うかは判らないが、G7の内、独り日本だけが、ビン・ラディン氏からも「無視」されたのである。